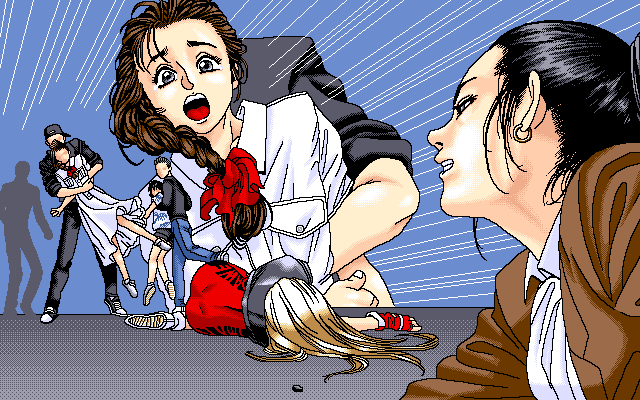
Illustration by Kunio Aoki
「白葉さん……どうも」
そう声をかけてようやく、白葉は坂井たちが入ってきた事に気付いたらしかった。よほど彼女との話に熱中していたらしい。
「今日は何の講義を?」
杜沢がそう言って笑顔を向けた。
「やあ、坂井さん、杜沢くん。いやいや、今日は講義と言うのではなくてですな……どちらかと言えばこのお嬢さんに私の方が教えてもらっていたようなものです」
「DGSの方ですね?」
女の着ている制服を見て、坂井はそう言って笑顔を作った。
「……はい、庶務課に勤めております、嶋と申します。あの、教授、こちらの方は?」
「ああ、うちの学部と懇意にしてもらっている味噌屋さんです。このとなりに「こうじや」さんという店を構えていらっしゃる。えーと、それからこちらは大学の博物館で館員をしている杜沢くん。「こうじや」さんのお得意さんのひとりです。……私と並んでね。――ああ、坂井さん彼女は今日初めてこの店に来たそうなんだが、バイオスフィア計画に興味を持っているようでね。その話をしていたんだが……」
「DGSがバイオスフィア計画に参入するという噂は本当だったんですか」
坂井が口をはさんだ。嶋と名乗った女に勧められて同じテーブルを囲む。
「さあ、私にはあまり詳しい事は……。でも毎日のようにテレビで放送していますから、やはり自然と目が行くようになって。ドイツにある本社から宇宙開発企画室の人が来日しているっていうことですし、案外話は進んでいるのかとも思ったんですけれど……教授のお話ではそういうことでもないらしいので、ちょっと残念だわ。私はうちの社がバイオスフィア計画に参加しても、計画に関係のある仕事ができるほどの身分ではないんですが」
「いや……何しろ、実験の方がなかなか進まないような状態で、しかもあれでしょう、えーとですな。佐々木建設の社長が亡くなったりで……。世間ばかりが騒いでいるような状態なんですよ。計画事態が大きなものですからね、都も絡んでおるわけだし。企業サイドの話もなかなかスムーズには進まない。佐々木建設からもDGSからも、まだ公式の話は来ていないような状態でしてね」
白葉はそう言って千尋の運んできたお茶をすすった。
坂井と杜沢がそれぞれ千尋に納豆定食、コロッケ定食を注文する。
「ついさっき、食事に出ようとしたら急にお客さんがきてしまいましてね。うちは、お客がくると長いですから……すっかりお腹がすいてしまいました」
「え……? あら、いけない。帰らないと昼休みが終わってしまうわ。……教授、今日はいろいろありがとうございました。私、バイオスフィア計画にますます興味が出てきましたわ」
そう言って、嶋は立ち上がった。
「あ、ああ。また来たまえ、嶋くん」
「納豆定食お待ちどうさまです。……あの人、このお店に来るの初めてって言ってました、よね?」
定食の盆を運んできた千尋が嶋の出ていった扉をちらりと振り返って白葉にそう聞いた。
「ん? ああ、そう言っていたが……」
「どこかで見た事があるような気がするんだけど……気のせいかしらね。あ、杜沢さんのコロッケ定食、今持ってきますね」
千尋はあまり気にも止めなかった様子で、ぱっと身を翻した。
だが、坂井の方は気付いていた。
嶋と名乗った女の一癖ある匂いのようなものが、彼女がただの庶務課のOLなどではない事を悟らせたのだ。テレビや写真ではその姿を何度も見たが、実際に会った事はないので、断言はできない。だが……確信に近いものを坂井は抱いていた。
(あれは……椎摩渚だ)
ウィッグをつけ、コンタクトレンズであの瞳を隠し……巧みな化粧で顔の印象を変えても、はっと目を引くその際だった容貌は隠しようがない。女のことにあまり頓着のない白葉や杜沢は気付いていないようだったが、巧妙に「ふつうの女」を装いながら……嶋と名乗った女には、決して「ふつうの女」でいる事を許さない色香があった。坂井の他にその事に気付いたのは……恐らく中嶋千尋くらいだっただろう。
そして、ふと定食の盆に視線を戻したとき、坂井は嶋の出て行った扉をぼーっと眺めている杜沢の視線に気付いた。
「どうしたんです? 杜沢さん、ぼんやりして」
「え? ああ……何でもありません」
杜沢も……あるいは気付いていたのだろうか、と坂井は思った。だが、杜沢の考えていた事は、もっと別の事だった。
DGSという組織を……これまで椎摩渚や神野麗子という幹部たちの印象だけでひとくくりにしていた杜沢にとって、嶋の言葉は新鮮な驚きを与えるものだった。DGSの中にも……純粋に計画に熱意を持っている社員がいるのだと、改めて感じたのだ。
(彼女と……もう少し話をしてみたい。DGSがどんな思惑を抱いてバイオスフィア計画に参加しようとしているのか……マスコミの報じているのとは違う側面があるのなら、それを調べてみなければならない)
杜沢はそう考えていた。
もちろん、庶務課のOLが純粋に熱意を持っているからといって、それが会社を動かす力にはなり得ない事は、企業という組織にこれまで一度も入った事のない杜沢にも分かっていた。そしてDGSは……全世界に広がるネットワークを持つ、巨大な企業なのだ。
「白葉さん……実はちょっとお願いがあるんですが……」
そんな杜沢の思惑には気付かず、坂井は白葉に視線を投げた。
「なんでしょう?」
「会って頂きたい人がいるんです。白葉さんの携わってらっしゃるバイオスフィア計画のことで……ぜひともお会いして、話を聞きたいという人が……」
「誰なんでしょうかね? それとも匿名で?」
「いえ……、佐々木建設の次期社長です」
「……義一くんですか。しかし……なぜ坂井さんが?」
坂井の表情と、トーンを落とした声の調子から、白葉はそれが決して表沙汰にする事はできない状況なのだと悟ったようだった。そして坂井は、「次期社長」という言葉から、白葉が躊躇する事なく義一の名前を出したことに安堵感を抱いていた。
(……やはり、白葉さんはマスコミの浮ついた報道に動かされる人ではない)
そう、強く感じさせるものが白葉の言葉にはあった。
「私は佐々木建設の隠密なんです」
「……」
一瞬、白葉は言葉を失った。
今時珍しい職人堅気の坂井が、真顔で「隠密」などと言う言葉を口にするとは思ってもみない事だった。
「隠密とはまた……穏やかじゃありませんな」
「……多少、込み入った話になりますが……お時間を頂けますか。ここではちょっと何ですから、私の店に行きましょう。奥の座敷でなら聞き耳を立てる者もいません」
そう言って、坂井は箸を置いた。
後にも先にも、彼が紀美枝の作った料理を残して席を立つのは初めての事だった。
坂井とのつき合いはずいぶん長くなるが、その白葉も、座敷まで上がった事はなかった。味噌を買った後、そのまま店舗で話し込むか、でなければ隣の『味の屋』に場を移して食事をしながら……というのがいつものパターンだ。
「狭いところで……申し訳ありませんね」
そう言って坂井は白葉に座布団を勧めた。
「お気遣いは無用です。……で、坂井さん、お話を伺いましょう。あなたと佐々木建設はどういう関係なんです。隠密とは、どう意味なんですか」
「亡くなった辰樹さんとは高校の同級生でしてね。まあ、そういう縁もあって私は一度は佐々木建設に就職したんです。……その頃から、将来、宇宙開発に関して有事の際には裏から彼の夢を助ける、という約束をしていました。佐々木建設の警備部で窓際を暖めながらね。辰樹さんが社長に就任する際にも、色々ごたごたがありましたから、その時もちょっとしたお手伝いをさせてもらったんです」
「……手伝い、とはどういうことですかな」
「辰樹さんの社長就任に反感を抱く重役をピックアップしたと言う程度です。表向きは味方のような顔をしていても、裏で画策をしているというような重役が何名かいましたから……宇宙進出と言うのは金のかかる事業ですから、やはり重役も慎重になります。辰樹さんはあの通り、自分の信念をおおっぴらにしたがるところがありましたから、社内にも敵は多かったんです」
「そして、今度もそうだと?」
「ええ。……白葉さんもDGSのパーティの報道をご覧になったでしょう。ああいった事から義一さん……いえ、佐々木建設の宇宙進出の夢を守る事が私の仕事なんです」
「夢を守る仕事……ですか。辰樹さんらしい」
白葉はようやく、怪訝そうな表情を崩していつも通りの笑顔を浮かべた。
「義一くんが会うと言うのなら……何とか時間を都合しましょう。いつがいいですかな」
(庶務課だと言っていたな。……真奈美ちゃんに頼めば会えるように手を打ってもらえるかも知れない)
表の引き戸がからりと開いたのは、その時だった。
「いらっしゃいま……」
そこまで言って、杜沢は言葉をとぎらせた。
開けた扉の前で立ちすくんでいる男の顔を見つめて言葉を失う。
「……浩二さん」
「こうじや」を訪ねてきたのは、佐々木浩二だった。
杜沢がそこに立っているのを見ても、浩二には驚いた様子はなかった。むしろ、杜沢がいると思ったからこそここを訪れたのだと言う表情を浮かべている。
「こんな気が……してたんです。杜沢さん」
ちょうど、白葉と坂井の話が終わったところだった。
奥の座敷と店舗とを仕切っている襖が開き、白葉が顔を出した。
「佐々木浩二くん……」
白葉もまた、浩二の来訪に驚きの表情を見せていた。
そしてその白葉の背後に立った坂井が、浩二の顔を見つめ、軽く会釈をする。
「来て下さると思っていましたよ……浩二さん」
「兄がひとりアメリカに渡った後――西崎さんをはじめとする重役たちの視線はいつも僕に向けられていました。父の宇宙開発への野心は、すでに多くの重役にとって邪魔な存在になっていたんです。兄が留守をしているうちに僕を次期社長候補に据えて、父を社長の座から追うことを彼らはその頃から画策していたようです。僕には、あまりそういう下心を見通すだけの力がなくて……そのために彼らに利用されるような形になってしまった。佐々木建設の株が暴落したのも、あんな風にDGSに付け入られたのも……みんな僕が不甲斐なかったせいです。この間、水産試験場で杜沢さんにお会いして色々話しているうちに……なんて言うか、自分の中にある力みたいなものの存在に気付いたんです。父があんなにも強く宇宙を目指したように、兄が追いつめられながらも父の遺志を受け継ごうとするように……僕にも戦う事が必要なのだと、そう悟ったんです」
卓袱台を囲んだ坂井、白葉、そして杜沢の顔を順番に見回して、浩二はまるで独り言のように淡々としゃべった。
「……今、坂井さんとも話していたんだが、来週、義一くんと会う事になった。義一くんがあなたの言う通り辰樹氏と同じ情熱を持っていると言うのなら、農工科はこれまでの姿勢を崩す事はしない。しかしそれは同時に君が社長の座を諦めるという事だ。それでいいのかね? 君は社長になり、環境問題に取り組む総合企業に佐々木建設を育てていく熱意を持っているんじゃなかったのかね」
白葉は浩二の顔をのぞき込むようにして言った。
その白葉に、浩二は穏やかな笑顔を向けて頷いた。
「あの言葉は……椎摩さんがでっち上げたものですが、僕の心の中を見透かしていたものだったとも言えます。宇宙開発に情熱を燃やす余り、そう言った方面に父はあまり目を向けていませんでしたからね。もし兄が膝を折るのなら……私が社長になると言うのなら、彼女の言っていた言葉は決して嘘ではありません。でもその夢も……兄が受け継いでくれます。兄が私より確実に、佐々木建設を環境問題に真正面から取り組む企業に、そして宇宙に根を降ろす企業に育ててくれるのだと……信じています。兄にはそれをする力がある」
「では……浩二くん。君は自分の夢を諦めるのかね?」
「いえ、そうじゃありません。僕の……佐々木建設とは別の場所にある夢を叶えるために、兄にすべてを託すんです」
「……別の場所にある夢、とは?」
「この人工群島に、水族館を作ることです。各地の海洋汚染、アマゾン川の水質汚染、アフリカのタンガニーカ湖の開発……さまざまな場所で絶滅に瀕している生物たちを守る第一歩として……。訪れる子供たちに魚の話を聞かせてやって……その魚たちの生きるべき場所が壊されているのだと言うことを教えてやりたい。そしてその子供たちの中から、父のように、兄のように……あなたのように地球の未来を考える人材が育つのを見守っていきたいんです」
その浩二の言葉は彼の気弱な印象を払拭するほどに力強いものだった。
そして白葉の心を動かすほどに……その言葉は情熱に溢れていた。かつて辰樹が白葉のもとを訪ね、宇宙ホテル建設の野望を語ってくれたときの事を白葉は思い出していた。
同じように今、自らの大きな夢を語る浩二の表情は……椎摩渚の隣で自分に注がれる無数の視線を避けるように頭を垂れていたニュースの映像とは、まったく違うものだった。
(彼もまた……辰樹氏の息子なのだ)
そう白葉は感じていた。
洋上大学附属の博物館の館員杜沢跡見が庶務課の嶋に面会を申し込んだ……という話を椎摩渚は受付から庶務課、秘書課を経由してチャン・リン・シャンの口から聞いた。
嶋というOLが椎摩の変装だとチャンはすぐに気付いたらしい。
DGSの就業規則に従って、受付の女は面会を断ったということだったが、杜沢は近くの公園にいますと言う伝言を託していた。
ちょうど交代の時間で、受付にいたのは真奈美ではなく……大手の派遣会社から来ていたもうひとりの受付場の方だった。それで杜沢は食い下がる事をせずに面会を諦めたのだ。
(杜沢跡見……あの男が何故?)
渚はその連絡を無視しきれなかった。
はっきりと言葉にする事はできない……予感のようなものを感じたのだ。
『味の屋』を訪れたときと同じようにコンタクトレンズで瞳の色を隠し、ウィッグをつけて化粧を変え、DGSの女性社員の制服に身を包んで、渚は部屋を出た。
杜沢はまだ公園にいるはずだ。
そう確信させたのは、彼女の生来の自信のせいだったのかもしれない。
西崎らのテロから渚を守るためにエヴァゼリンとともに来日していたコンラート・ハイドリッヒに離れた場所から自分をガードするように命ずると、杜沢のいる公園に向かった。
公園のベンチに座って、杜沢はぼんやりと辺りの景色を見つめていた。もうしばらく待って、それでも来なければ嶋と会う事は諦めるつもりだった。
杜沢のいる場所からはDGS極東支部ビルが見える。
風が少し強くなり、杜沢の伸びた前髪を吹き上げた。それをうるさそうにかき上げたとき、杜沢は公園の遊歩道をゆっくりと歩いてくる嶋の姿を見つけた。
いや、その瞬間、杜沢は『味の屋』で坂井が感じたのと同じ彼女の「匂い」を嗅いだような気がした。そしてその感触は……坂井よりずっと強いものだった。
(椎摩……渚)
ニュースの映像で何度も見た渚とは目の色も髪型も……雰囲気までもがまったく違っているのだが、杜沢は直感と言ってもいいだろう鋭敏な感覚でそれを悟った。
「わざわざ来て下さったのに……申し訳ありませんわ。うちの会社、規則が厳しいんです。約束のない面会はよほどの事がないと取り次いでもらえなくって……。それで、どういうご用かしら?」
「……バイオスフィア計画と佐々木建設のことで、お話を伺いたいんです。椎摩さん」
その杜沢の言葉に、渚の表情が堅くなった。
そして彼女からは5メートルほど離れたベンチに腰を降ろしていたハイドリッヒが、ゆっくりと立ち上がり、杜沢を警戒するように近づいてきた。
「あなたがバイオスフィア計画にどんな関心を寄せているのか……それをお聞きしたいんです。もしあなたが純粋にあの計画に夢を抱いているのなら、なぜ佐々木建設と協力して計画を援助することを考えないんですか? どうして佐々木建設を手中に取り込まなければならないんです。……申し訳ありません、不躾だとは分かっています。企業同士の問題は……そんな単純な事じゃないっていうのも、確かにあるでしょう。でも……」
杜沢はこれまで佐々木建設とDGSとの泥試合をはた目に見て、ずっと思い続けてきた事をつい口に出さずにはいられなかった。
さまざまな利権の絡んだこのプロジェクトが、彼らにとって独占してこそ意味のある事なのだと言うことを考える発想は、学者馬鹿の杜沢にはまったくない。ただ……その泥試合の中で……正々堂々と勝負を望んでいたはずの義一が隠密を使って裏工作を強いられ、浩二が利用され、真剣に佐々木建設の将来を憂いて宇宙開発に反対している重役たちが私欲に走った西崎と同列に見なされているのを……辛いと感じているだけだった。
「私は一介のOLですもの。そういう難しいお話は良く分からないわ」
渚はそう言って杜沢を見つめ、ハイドリッヒに「まだ動くな」と小さく合図を送った。
「でもね……杜沢さん。これだけはあなたも理解するべきだわ。どういう形であれ、この戦いに関係した者としてね。DGSにとっても佐々木建設にとっても……夢は野心を満たしてこそ叶えられるものなのよ。だからこそ佐々木辰樹氏は亡くなり、義一氏は追われているんじゃなくて?」
渚はそれだけ言って身を翻した。
その渚の後を追うようにハイドリッヒも歩き始める。
もう彼女は杜沢を振り返ろうとはしなかった。
DGSに戻った渚はビルに入ろうとしたとき……通りの反対側に西崎の姿を見たような気がした。
(……!)
背後に立っていたハイドリッヒに西崎を捕らえるように命じようとしたが、すでにその時には西崎の姿は雑踏にまぎれて見えなくなっていた。
(まだ悪あがきを続けるつもりなの……西崎!)
そう言って、真奈美はポシェットに納められていた「七つ道具」をテーブルの上に並べて自慢そうに中川に見せびらかした。
「何が七つ道具だよ。たまの日曜日だってのに……ゆっくり寝かせてくれたっていいじゃないか」
「社長さん、いつだってゆっくり寝てるじゃないですか。ホントに凄いんだから。見て下さいってば」
別に、中川も仕事をしていないわけではないのだが……あまりそれらしい素振りも見せないので真奈美には遊び回っているように思われているのだ。
悪戦苦闘していた新型コンピューターのマニュアルを放り出して、しかたなく中川もダイニングの方へ顔を出す。その背後で中川の投げ捨てたマニュアルを拾い、アインシュタインがいちいちうんうん、と頷きながらそれを読み、中川が野村からせしめたアダルトゲームを立ち上げているのには、もちろんまったく気付いていない。
「ええとね、これが水に溶けるメモ。それから超微細ビデオカメラ付き猫の首輪。あ、これアインシュタインにつけて上げようかなあ。それからね、これが指輪型専用通信機。社長のとペアでもらっちゃったんです。はい、これ社長さんの分ね。あ、社長さん結構指細いんだあ。薬指じゃゆるゆるだなあ。しょうがないから中指につけててね」
「結婚指輪じゃあるまいし……薬指だろうが中指だろうがこんなもん付けてられるか」
そう言って、中川は真奈美が強引に中指に押し込んだ指輪を抜き取ろうとした。だが、抜けない。
「その指輪、着脱防止装置が付いてるんです。それから男性用だけは無理に引き抜こうとすると爆発する自爆装置がついてるって三宅のおじさま言ってました(^_^)」
「……お、おまえって奴はぁ。そういうことははめる前に言えよな」
「大丈夫。たまに暴発もするけど死ぬ事はないって言ってましたから」
「……しまいにゃ犯すぞ、てめえ」
「あ、あとね……これが自爆装置付き腕時計。痴漢撃退用にも使える爆発音だけの装置なんですって。あとこれが、小型拳銃型スタンガン。太股につけなきゃダメって指定されちゃったんですよー。ちょっとエッチですよね」
「そういうヒヒ爺から気安く物をもらうなよ……(^^;)」
「社長さんじゃあるまいし……三宅のおじさまそんな人じゃないですってば。それからこっちがね、スパイの心得入り電子手帳。ねー凄いでしょ?」
中川は指輪との格闘を早々に諦め、電子手帳に手を伸ばした。
「スパイの心得」と書かれているボタンを押してみる。
| 1.寝早起きしよう。 2.食事の後は忘れずに歯磨きしよう。 3.道路で遊んでは行けないよ。 4.……………… |
ディスプレイに表示されたのはそれらの文面からなる10の項目だった。
「こりゃあ大層役に立ちそうな心得だ。おぢさんびっくりしちゃいましたよ」
うんざりしたように言って、中川は電子手帳を放り投げる。
「七つ道具って言うけど、六つしかないじゃないか」
「えー、七つ目はこの万能ポシェットですよ。決まってるじゃないですか」
それに至っては、もう聞く耳なんか持ちたくないと言うレベルの返答だった。初対面の中川にお茶の講義をぶったあの白葉というハイパー教授にしろ、どこから真奈美がスパイだって事を嗅ぎつけたのかは知らないが、こんな役に立つんだか立たないんだか分からないようなスパイセットを用意する三宅とか言う教授にしろ……洋上大学の教授はそういう変人ばかりなのだろうかと頭を抱えてしまう。
わずか7カ月で大学をドロップアウトしたことを……中川は今は賢明な判断だったのだとさえ考え始めている。ちなみに中川は洋上大学経済学部に籍を置いていた。置いていただけで、講義には二回くらいしか顔を出した事はない。
「どっか出かけるのか?」
「チャンさんがデートに誘ってくれたんです。オープンベンツに乗せてくれるっていうからOKしちゃった☆ ちょっとエッチだけど面白いんですよ、チャンさんって。社長さんは? 今日はお出かけしないんですか?」
「あ? ああ……出かける事になるかもしれないな。例の石岡って奴の事少し調べときたいからな。あの後はもう来てないんだろう?」
「来たってあの会社の警備員が怖くて入れないんじゃないかなぁ。ぼこぼこに殴られてたみたいだから。神野さんってコワイ人なんですよ。調べるって……どうするんですか? あの人もう佐々木建設も辞めさせられちゃったんでしょう?」
「あいつは吉沢さんとこからの派遣社員だからな。そっちから調べれば何とか。まあ、どっちにしたってもう佐々木建設からもDGSからも放逐された身の上だから、調べたところであんまり意味はないとも思うんだけどな」
その中川を、真奈美は意外そうな表情で見つめていた。
「社長さんがそんなに仕事熱心なところ、奈美初めて見ちゃった。じゃあ、行ってきまーす」
(言ってろよ)
内心そうは思っても口にも顔にも出さない。
これでなかなか、照れ屋な男なのである。
そして真奈美の出て行った部屋で、中川はなぜか立ち上がっていたアダルトゲームのディスクを抜き取って吉沢建設の人材バンクにアクセスした。これは半ば吉沢派遣の下請けとなっているゼロワンSTAFFを始めいくつかの小規模な人材派遣会社むけに後悔されているものだった。
「ウキキッ(しゃちょうさん、まなみちゃんのわすれものです)」
「ん? なんだ、ちょっと待ってろよ。これが終わったら飯にしてやるから」
取りあえず、中川はアインシュタインが何か意思表示をしたときにはご飯をやればいいと思っている。そのためか、最近ちょっと太ったような気がするアインシュタインではあった。
「ウキキッ(とどけたほうがいいですか? なんだったらいまからひとっぱしりいってきますけど)」
「うるせえなあ。ちょっと黙ってろよ」
そう言いながらも中川がアインシュタインの方に視線を向けたとき、アインシュタインは小型拳銃型スタンガン――つまり真奈美が三宅教授からもらったスパイセットの一品を中川の方に向けて構えていた。
そして次の瞬間。
びりっ!
……という痛みとも痺れともつかない感覚が中川を襲った。
「ウキキッ(しゃちょうさん、どうしたんですか?)」
そのアインシュタインの声は昏倒した中川には聞こえていなかった。
どこまでも……不幸な男である。
「DGSが躍起になって探しているだろうに……いつまでもこんな所にいるとは思いませんでしたよ。……お父さん」
だが、佐々木建設の副社長として君臨していた頃のふてぶてしいまでに自信に満ちた表情を失い、やつれ果てた逃亡者となった西崎の姿を見おろす高槻の表情は、侮蔑の込められた、冷酷なものだった。
「追いつめられて……八方塞がりだ。裏金を凍結されて、もう私の手元に残っている金も残り少ない。自宅はもちろん、女房の実家までDGSに張られているんだ、他にどこに行く場所がある。だがな、洋二……私はこのまま惨めな敗北者にはならんぞ。浩二の事など、もうどうでもいい。本当に力を持っている、社長にふさわしい男は義一の方なんだからな」
「待って下さい、お父さん。いえ……西崎元副社長」
高槻がそう口をはさんで初めて、西崎は自分を見おろす高槻の……冷たい視線に気付いた。
「……洋二。なんだその目は! お前まで私を見捨てようと言うのか? 私が不義の子のお前に情けをかけて拾い上げてやらなければ……佐々木建設のような大手企業に就職する事などできず、貧乏サラリーマンの小倅で終わっていたんだぞ。誰のおかげで……!」
「私を副社長秘書に取り立ててくれたのは……義一副社長ですよ。あなたは私が入社するとき便宜をはかってくれただけだ。もっとも、あなたの力など借りなくても私は佐々木建設に入社するつもりでしたがね。母から……あなたというもうひとりの父親の存在を打ち明けられたときから」
「なんだと? 貴様……これまでの恩も忘れおって」
「恩……? あなたからそんな言葉を聞く事になるとは思いませんでしたね」
高槻は静かにそう言って、窓際の椅子に腰を降ろした。
テーブルに置かれているインスタント食品の開き容器が……西崎の逃亡生活の貧しさを語っているようでもあった。
薄汚い部屋の中でよれよれのワイシャツをズボンからはみ出させている西崎の姿は醜悪なほどに情けない。それを自分の父親だなどと思いたいわけはなかった。
「辰樹があんな事故で死にさえしなければ……義一がこんなにはやく帰ってくる事もなかった。私は浩二を次期社長にするための地場固めをすることができ……」
「あの交通事故に……感謝するべきなんじゃないんですか。あの事故で辰樹が死んだからこそ、あなたは自分の手を汚す事なく、目の上の瘤だった辰樹を葬り去る事ができたんだ。もっともそのざまを見れば……満足に殺人などできない男なのかも知れませんがね、え? どうなんだよ、西崎。辰樹を殺し、その後がまに浩二を据える計画を私に立てさせて……それを見つめてほくそえんでいるだけで……実のところ実行に移す度胸などなかったんじゃないのか? 私が手配しなければ……あの時義一に脅迫状を出す事さえ思いつかなかったお前が……いったい何をできたって言うんだ」
高槻の顔は怒りに歪んでいた。
辰樹の正当な息子として……生まれたときから命令を下す側にいた義一に、これまで抱き続けてきた嫉妬と羨望がどす黒い渦のように高槻の身体の中に逆巻いていた。
だから高槻は浩二を次期社長に据えるという西崎の案をこれまで影で支え続けてきたのだ。
だが、その結果がこの西崎の憔悴しきった姿だった。
椎摩渚の身体に溺れ、自分を見失って調子に乗った挙げ句に、DGSから遊び飽きた玩具のように捨てられて……この土壇場で高槻にすがり、義一の側に寝返ろうとしている。
その光景は高槻にとって……義一への敗北を突きつけられたのと同じだった。
一代で社を業界の頂点にまで育て上げた野心家の長男として生まれ、実業家となる男なら誰でも欲する能力と幸運とに恵まれて……自分こそが次期社長にふさわしいと考えているあの義一が、妾の息子にその座を奪われ失脚する姿を見る事こそ……高槻の思い描いていた結末だったと言うのに……。
「あなたの時代は終わったんですよ。……私は母の過去の過ちは忘れます。父がそうしたようにね。しょせんあなたには、佐々木建設は大きすぎる夢だったんだ。それを……そろそろ悟ってはどうです」
「……る、さんぞ」
西崎が、口の中でもごもごと何かを言った。
「許さんぞ、洋二! 私を見捨てる事など! お前は私の息子だ! 私はお前の……」
そう喚きながら飛びかかってきたとき……高槻はすでに西崎の精神が均衡を失っている事に気付いた。
だが……そう気付いても、もう遅すぎた。
高槻の身体を引き倒して馬乗りになった西崎の震える手には、刃渡り十五センチほどの果物ナイフが握りしめられていた。まだ真新しいそのブレードを見つめ……そのナイフこそ、西崎が辰樹を殺すために用意した物なのだと悟った。
二十数年の間……西崎の前にはいつも辰樹の背中があった。
その背中を見つめ、この男はいつも殺意をたぎらせていたのだ。
辰樹の能力を、辰樹を育てた環境を……辰樹の抱いた野心を、そして義一という辰樹の息子……辰樹の夢も野心もすべてを受け継ぎ、さらに大きく育て上げる力を持った後継者を、西崎はいつも嫉妬と羨望のまじりあった視線で見つめ続けてきた。
私には、決して辰樹を超える事はできない。
その歴然たる事実が、いつも西崎を脅迫し続けていた。
「お前は死んでも……俺をあざ笑い続けるのか……辰樹!」
醜い劣等感に歪んだ顔が、高槻の目の前にあった。
そして次の瞬間、下腹に鈍い衝撃が走った。
狂気に浮かされたような西崎のうすら笑いが赤く染まった視界にくっきりと刻み込まれる。衝撃は一度にとどまらなかった。
意識が途切れるまで……高槻はその激痛を何度も感じ、満足に動かなくなって手足をふりまわしてもがいた。
だが次第に、その抵抗も力弱い物になっていった。
「西崎副社長!」
鋭い声が響き、部屋に飛び込んできた牧田がナイフを振り上げる西崎を止めたとき、すでに高槻はこと切れていた。
「洋二……洋二さんっ!」
牧田は血塗れになった高槻の身体を揺さぶった。
すでにその腹部はメッタ刺しにされ、血の海の中に白く脂肪の浮き上がったおぞましい姿になっていた。破裂した内蔵から溢れ出た液体の悪臭が部屋中に立ちこめている。
「何故です! どうしてこんな事に……」
「牧田、手はずは整ったのか?」
「ええ……この19号埋め立て地にたむろするヤクザ連中を集めました。金のために何でもすると言うだけでなく、軍事学部崩れなどの腕を兼ね備えた者たちです。しかし、そんな事より今は洋二さんを……」
「……人を殺すのが、こんなにたやすい事とは思わなかった。あんな交通事故で辰樹を死なす前に、私がこの手で殺してしまえば良かったんだよ。そうすれば……」
「副社長! しっかりなさって下さい」
「辰樹の娘を手に入れるんだ。……そうすれば義一は一も二もなく私に従うだろう。あの男は冷徹そうに見えて、血の絆に脆いところがあるからな。妾の息子である浩二をさっさと蹴落とす事ができずにみすみす敵に回したのも、その脆さが原因だ。やれるさ、牧田。あの娘を使って義一を脅し……私の副社長としての立場を確保するんだ。DGSの裏取り引きの情報もすべて奴にくれてやる。義一は社長になりたいだけの野心家だ。社長の座に据えてしまえばそれでもう用はない」
その西崎の言葉から、牧田もまたこの男がすでに正気でない事を悟っていた。
だがそれでも、もう牧田には西崎と運命を共にする以外の逃げ道はなかった。義一は無能な二代目などではない。そして、裏切りを決して許さぬ冷徹さがあった。
それでもこうする以外に……牧田にとってももう一度のし上がっていく方法はないのだ。
それが例え、破滅に向かって突っ走る行為であったとしても……。
「焼き肉定食追加ね」
「あ、じゃあね、香南は大盛り野菜炒め定食。納豆とほうれん草のおひたしもつけてね」
店の真ん中のテーブルを陣取って、すでに双方とも三度目になる追加注文を叫んだ。
ご存知北海珍味娘森沢香南とジーラ・ナサディーンの大食い勝負だった。
『味の屋』でバイトをしている双子の妹シーラに、
「『味の屋』にときどき来る女の子がいてね、ああ、この間イカの薫製持ってきたでしょ? あれ売りつけた子なんだけど……すごい大食らいなの」
という話を聞いて、
「そんな見所のある子がいるなんて思わなかったわ。勝負してみたい」
……などと思い立ったこの勝負の発端だった。
そして折りよく、今日……暇を持て余していたジーラのもとに香南が北海の珍味を担いで現れたのだ。
「買ってくれないなら、せめて幸せの踊りを踊らせて下さい」
と、いつも通りのパターンで食品サンプルを並べ始めた香南に、ジーラが勝負を申し込んだのだ。
「そんなまどろっこしいことは必要ないわ。ストリップでもやってくれるんならともかく、あんたの下手な踊りなんか見たって面白くもなんともないのよね。それよりこれから『味の屋』に乗り込んで大食い勝負としゃれこまない? もしあんたが勝ったら今持ってる北海の何とか、全部買って上げるわ」
「うん、香南、やる!」
負けた場合の事は、香南は尋ねてはいない。
そしてジーラも特に考えていなかった。ジーラにとっては勝負の結果はあまり意味がない。言ってみれば香南は彼女の「ちょうどいいひまつぶし」なのだ。
……という経緯で、香南とジーラは『味の屋』に入り、定番の納豆定食から始まって、鯵フライ定食と豚カツ定食(香南)、焼き魚定食と肉じゃが定食(ジーラ)を経て、三度目の追加注文にこぎ着けたところなのである。
周囲の客の反応は、大きくふたつに分かれた。
つまり、
「……なんか今日は食欲なくなっちゃったなあ。ごちそうさま……また来るよ」
という食欲減退派と、
「どっちが勝つか賭けないか、一口五千円くらいで」
というトトカルチョ派のふたつである。
中には食欲を減退させつつトトカルチョに走った客も数名いる。
だがしょせん、香南もジーラの敵ではなかった。
三度目の追加注文の野菜炒め定食をつつきはじめた辺りから、旗色がぐっと悪くなってきたのである。
「……も、もうダメだぁ」
箸を投げ出した香南に、水と胃薬を差し出しながら、
「ダメよ、ご飯残しちゃ(^_^)」
と言い放った紀美枝ってすごいスゴイ大物だと、ジーラは思う。
「あー、良く食べたわ。でもまあ、香南、あんたもちびの割には大したもんよ。うんうん。気に入ったわ」
焼き肉定食を悠然と食べ終えて、ジーラはにっこりと笑った。
(……化け物)
と思ったのは、香南ひとりではなかった。
そしてジーラに賭けていた連中が、換金をしている真っ最中の『味の屋』に、新たな騒動の種が乗り込んできた。
「やっほー。ジーラがここにいるって聞いたんだけど。あ、いたいた。ねっ、見て見て。うちの会社の新しい受付嬢なの。可愛いでしょー。今デートの最中なんだ。ねぇ、ジーラも一緒にドライブしない? 会社からスゴイ車借りちゃったのよ。運転したいと思わない?」
そう言ったチャンの背後には、例のパーティのオープニングセレモニーで椎摩渚の乗っていたオープントップのメルセデスベンツが、かもめ商店街のメインストリートを塞ぐような形で止まっていた。
もちろん、そんなヤバそうな車を相手に、喧嘩を売る者はいない。
クラクションひとつ鳴らす車もなく商店街は静かに渋滞していた。
「あれえ、香南どうしてこんなトコにいるの?」
チャンの背後から真奈美がぴょこんと顔を出した。
「ああ、この娘ね。うちになんか売りにきてたんだけど、退屈だったからちょっと大食い勝負してたとこなの(^_^)。なかなか筋はいいけど、まあ経験不足が仇になったってところかな」
大食い勝負にどんな経験が必要とされるのかは……取りあえず謎である。
ともかくその勢いで、チャン・リン・シャンと真奈美のデートに、ジーラ・ナサディーンと香南が乱入する事となった。
チャンがジーラを誘ったのは、単に彼女をこの車で暴走させるためではない。念のため。
西崎が真奈美を使って義一を脅迫しようとしているという情報を、あのパーティの夜に伊島プリンスを張っていた警備部の者から聞き、
「じゃあ、真奈美ちゃんを使って西崎もおびき出しちゃおう☆」
……と思いついたのだ。
別に下心だけで真奈美を誘いだした訳ではないのである。
ジーラは西崎が雇入れているのだろう真奈美誘拐のためのヨタ者たちを蹴散らすためのボディガードだった。
そしてチャンの狙い通り、西崎に雇われた連中は現れた。
『味の屋』を出た四人がジーラの運転するメルセデスで豊島マリーナに向かったところで、五人組の男に囲まれたのだ。
「いい車だなあ。それに可愛い娘もいるし……。ちょっと俺たちに貸してくれる? この彼女とそこまでドライブしたいのよね」
「や……なにするのよ、離して!」
(西崎の手のものにしてはまたずいぶん程度の低い連中だわね……)
チャンは多少いぶかしんだ。
こんな連中ならばものの五分と経たないうちにジーラが片づけてしまうだろう。
事実、チャンが何も言わないうちから、ジーラは安物のナイフを弄んで真奈美の肩に手を回していた男に掴みかかっていた。
「相手が悪かったわね……その汚い手でこの娘に触った事を後悔するわよ」
ナイフを手にした五人の男を前に、ジーラはそう言い放った。
そのジーラの言葉に、男たちがちょっと怯んだようにも見える。170センチ以上もある大柄な外人女にすごまれれば……こういうチンピラ風情が恐れをなすのも無理はない事だった。
だが、本当の敵はその五人ではなかった。
チンピラ連中に真奈美や香南はもちろん、ジーラとチャンも目を奪われていたために、背後に音もなく忍び寄った二人の男には気付かなかったのだ。
がつっという鈍い音が耳のすぐ側でするのをチャンは感じた。
そしてその瞬間がっくりと身体から力が抜け、その場に倒れる。
かすむ視界に、同じように鉄パイプで頭を殴られて倒れるジーラの姿が見えた。香南と真奈美の姿が見えなかった。
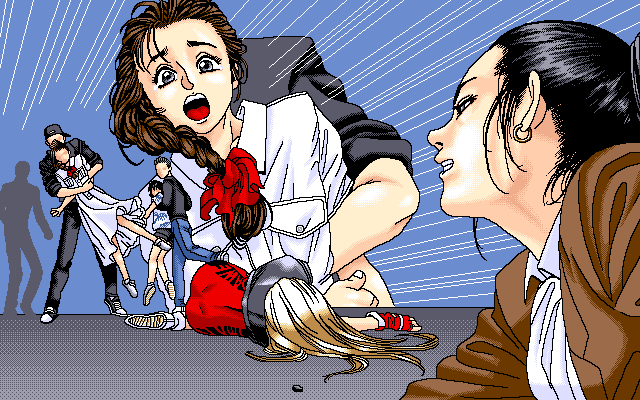
(く……やられ……た)
「チャンさん、チャンさん!」
そう叫ぶ真奈美の声が、かすかに聞こえたような気もする。
だが起きあがって真奈美を助ける力は……もう残ってはいなかった。
「離せってばぁっ! なにするんだ……この!」
香南の必死の抵抗もむなしいものだった。
手足の自由を奪われては、どうする事もできない。そしてその香南を、男はさっきジーラを殴り付けた鉄パイプで殴り付けて黙らせる。
「香南っ! 香南ってば!!」
真奈美はすぐ横に転がされている香南の名を叫んだ。
香南は切れた額から血を流してぐったりとしている。意識はほとんどないようだった。
「あの二人、殺してはいないだろうな?」
助手席に座った男が、背後の二人組を振り返って言った。
「あれぐらいじゃあ死にやしませんって。悪くたって廃人になるくらいですよ」
真奈美は助手席の男を見つめて思わず声を上げそうになった。そこにいたのは佐々木建設副社長西崎昌明だったのだ。
(逃げなきゃ……なんとかして逃げなきゃ、義一さんが脅迫される)
西崎の顔を見た瞬間に、真奈美は彼が何を企んでいるのかを悟った。
(お父さんの会社が、この人に脅迫される……!)
真奈美は、すでに佐々木辰樹が自分の父親である事に気付いていた。
スパイになるためにゼロワンSTAFFを訪れ、そして『佐々木ファイブ(仮)』の一員となったとき、坂井の見せてくれた辰樹の写真を見てその事を知ったのだ。
佐々木辰樹は……母・真砂美が今も大事にしている写真の男と同一人物だった。
その写真が、真砂美の持つたった一枚の父の写真なのだと気付いたのは……もうずいぶん前の事だ。
後ろ手に縛られていた訳ではなかったので、比較的手の自由は効いた。ふとその手に目をやって、真奈美は三宅のくれた指輪の事に気がついた。
これが三宅の言った通りの性能のものなら、中川に助けを求める事ができる。
「社長さん、助けて! 今豊島マリーナに……きゃあっ!」
真奈美は左手の薬指にはめた指輪に口を近づけ、思いきり叫んだ。
だがその瞬間、傍らにいた男が真奈美の頬を張りとばし、その指から指輪を抜き取った。真奈美用の指輪には、着脱防止装置はついていない。サイズの少し緩かった指輪はあっさりと抜け落ちた。
「三宅総研製……か。大方通信機でも仕込んでいやがるんだろう」
そう忌々しく呟いて窓の外に放り投げる。
「おい、こいつがどこに連絡したのかは分からないが、念のために車を変えるぞ。軍事学部校舎裏の駐車場へ回せ!」
香南が気絶してしまっている今、逃げ出すチャンスを見つけるのは難しい。だが、車を乗り換えるときを狙えば何とかなるかも知れない。……そう思って真奈美は太股につけたスタンガンに手を伸ばした。だが、
(……ないっ!)
スタンガンのホルスターはあるのだが、肝心の中身がなくなっていた。
出かける前に部屋で落としたのだが、もちろんそんな事には真奈美はまったく気付いていなかった。
(社長さん、早く助けにきて! このままじゃ、香南死んじゃうかもしれない……!)
『社長さん、助けて! 今豊島マリーナに……きゃあっ!』
中川の指にはめられた指輪から、真奈美のその悲鳴が響いた。
音量調節がうまくいっていないらしく、その声は三軒先まで聞こえるんじゃないかというすさまじいボリュームだった。
だが……昏倒していた中川には、その声を聞く事はできなかった。
「ウキキッ(しゃちょうさん、まなみちゃんがたすけをよんでるよ。このぶきのつかいかたもわかったし、まなみちゃんをたすけにいこう!)」
室内にそのアインシュタインの声がむなしく響いただけだ。
いくら揺り動かしても、中川はぴくりともしなかった。
「ウキキ?(しんじゃったのかな)」
そう呟いて……多少不安になり、中川の顔をのぞき込み、脈を取ってみる。取りあえず、死んではいない。
『しゃちょうさん、まなみちゃんがとじまありーなでたすけをもとめています』
手近にあった紙にそう書くと、アインシュタインはスタンガンを手に真奈美救出に向かおうとマンションの部屋を出た。
だが、『アブシンベル縁島』の前の道路まできて……自分が豊島マリーナの場所を知らない事に気付いて部屋に引き返す。中川が目を覚ますまで待つしかなかった。
豊島マリーナで真奈美を誘拐した男たちに殴り倒されたチャンは、通りがかった軍事学部の生徒に発見され、ジーラともども軍事学部の救護室に運び込まれていた。
チャンが目を覚ましたとき、すでにあれから二時間以上が経っていた。
(椎摩さまに連絡しなければ……)
チャンはふらつく足でベッドから降り、救護室の外にあるヴィジホンに向かった。
新型のコンピューターの使い方が良く分からないから、教えてくれと中川に頼まれていたアーマスは昼過ぎから日曜出勤する事になっていた。そして出勤してきたところで、なぜか気絶している中川と、アインシュタインの書いたメモを見つけたのだ。
「起きろよ、おい! 社長っ! 起きろってば!!」
そう叫んで、中川の身体を揺さぶる。
それでも起きないので、そのままずるずるとバスルームへ引きずって行き、頭から冷たいシャワーをぶちまけた。
「……ってえ……」
ぼんやりと中川が目を覚ましたところで襟首を掴み、その身体を引きずり起こす。
「しっかりしろっ! 真奈美が大変だ! 何が起こったのか分からないが……とにかく大変なんだよ!」
「真奈美が……? 畜生、身体に力が入らねえじゃないか、あの馬鹿猿め。ぶち殺してやる」
そう吐き捨てるように言いながら、何とか自分の力で立つと、びしょ濡れになったシャツを脱ぐ。ダイニングで電話が鳴ったのはその時だった。
「もしもし? 中川さん、大変です。真奈美くんが誘拐されたと言う知らせが今……」
「真奈美が……誘拐?」
「西崎です。西崎が真奈美くんを誘拐して義一さんに脅迫の電話をかけてきたんです」
中川の表情がさっと青ざめた。
それが西崎とDGSとの共謀作戦なのだと……中川の頭にいちばん最初に浮かんだのはその事だった。
チャン・リン・シャンと出かけると言っていたあの時に……止めれば良かったのだと言う後悔が沸き上がってくる。だがその中川の推理は、坂井の言葉によって打ち消された。
「西崎はDGSに捨てられて……それで真奈美くんを使って義一さんに佐々木建設での自分の地位を保証させようとしているようです。とにかく……すぐに来て下さい」
「あんたの所に行って、何ができるっていうんだ。それより一刻も早く真奈美を助け出す方が先だろうっ! いいか、おっさん、二十四時間の間は、俺とアーマスで真奈美を探す。だが、それ以上長引くようなら、あんたが何と言おうと……佐々木建設の体面がどうだろうと警察に行くからな」
「待って下さい、中川さん!」
だが、中川は坂井の言葉を振り返ろうとはしなかった。
「アーマス……お前、拳銃使えるか?」
「使えない事もないが……俺の拳銃は日本に来るときに処分して……」
「そんな事は分かってる」
中川はそう言い捨て、真奈美の寝室代わりになっているロフトに登った。敷き詰められたカーペットを剥し、床板を持ち上げてその下のわずかな隙間から三丁の拳銃を取り出した。
「弾丸はマガジンに入っているだけだ。……いいか、土壇場になって、他にどうしようもないって時以外、絶対使うなよ。お前の国じゃどうか知らないが、ここじゃあ拳銃一発撃っただけで警察は目の色変えるんだ。それを忘れるなよ」
取り出したうちの一丁をアーマスに押しやって、中川は念を押した。
戦う覚悟を決めている表情だった。
相手が西崎だろうと、DGSだろうと……そんな事は関係ない。真奈美を救うためにただ全力を尽くすだけだ。