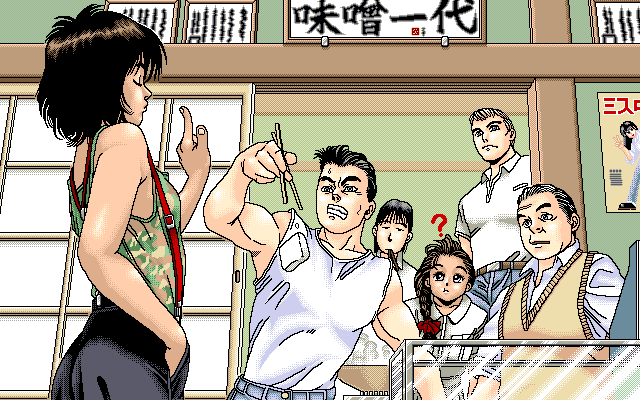
Illustrated by Kunio-Aoki.
足代わりに使っているオフロードバイクを道の脇に止め、地図にあったマンションを見上げてアーマス・グレブリーはため息をもらした。
(どういう趣味なんだ、いったい)
【アブ・シンベル神殿】(――しんでん);エジプト、ナイル川西岸、ヌビアのアブ・シンベル(Abu Simbel)にある古代エジプトの岩窟神殿。前1250年ごろ、ラメス2世の造営で、ハトル神をまつる。入り口にラメス2世の巨像(約20メートル)4体が、また中心の広間の8本の柱にはオシリスをかたどった同2世の立像がある。アスワン・ハイダム建設による水没を免れるため、ユネスコの後援により遺跡ごと約70メートル上へ移動(1968年完了)。 平凡社「世界史辞典」より抜粋
そんな知識がぼんやりと浮かぶ。
建物自体は、別にどうという事もないごくありふれた三流タイプのマンションで、その名にゆかりのある建物とは思えない(そんな事はあるわけがない)。
マンションの名前は、別に入居者の素性とは無関係だろうが、漠然とした不安を抱かずにはいられない。
「ゼロワンSTAFFって、デンジャラスな会社じゃないだろうな……?」
実はその通りなのだが、そんな事はマンションの名前を見るまでもなく気づくべきなのである。
群島プロムナードにスパイ募集を出すようなやつが、並の神経ではあるはずがない。
「別な会社にしたほうが良かったのかもしれない……」
そう気の早い後悔を抱きながら、アーマスはマンションに入り、エレベーターで5階に向かった。
アーマス・グレブリーはフリーのプログラマーである。
今日こうして中川のもとを訪れたのは、新しいプログラムの仕事先を得るためだった。それと言うのも、この人工群島に住み着いてからずっと世話になってきた会社の社長から突然、
「経営が思わしくないんでね。ちょっと人員整理をしたいんだよ」
と、肩を叩かれてしまったからだった。
能力の有無は、この際関係なかった。仕事を切っても退職金等の金のかからない奴から声がかかっただけの事だ。
そして、日夜プログラムを組む作業に没頭して、満足に人脈を作る事もでできなかったアーマスはめでたく路頭に迷う事となったのである。
これがアメリカでなら、仕事を捜す方法は知っている。しかし、いかんせんまだ日本の空気に馴れていないのだ。
そこで友人の勧めもあって、人材派遣会社に登録する事にした。
電話帳にあったいくつかの会社のうち、ゼロワンSTAFFを選んだ事に特別な意味はなかった。数日前に群島プロムナードでその名前を見かけていたので、きっと手広くやっている会社なんだろうと誤解したせいだった。
「プログラマーねえ」
見様見真似であぐらをかいて、窮屈そうにしているアーマスと、半分英語、半分へたくそな日本語という読み辛い履歴書を見比べて中川は頭を掻いた。
「ウチはこういう、小規模な会社なんでね……得意分野の募集以外は大した仕事回ってこないんですよ。得意分野ってのはオフィス・コンパニオンって言って、まあ要するにオフィスの雑用係なんですけどね。そりゃあまあ、プログラムの仕事だって紹介できないでもないですよ。でも、ちっちゃい会社ばっかりですよ。プログラムの片手間に電話取ったり、車の運転頼まれたりするような……。普通はね、そういうトコに押しこんじゃうんですけどね、適当に、うまい事言って。でもあんたの場合、それもあんまりねえ。日本語もそれほど達者じゃないみたいだし」
「プログラマーじゃ食ってけないかなあ」
「ないことはないですけどねえ……」
ちらちらとアーマスの表情を伺いながら、中川はじらすように話を引き延ばした。
実は仕事はあった。
それも、ゼロワンSTAFFには珍しい程好条件の在宅プログラマーの募集依頼だ。だがその仕事にアーマスを回したくはなかった。
(こいつなら使えそうだ)
……という、当てずっぽうが20パーセント、希望的観測が45パーセントくらい含まれた仕事師の勘というやつだ。
アメリカ人のアーマスをスパイとして使うのは、確かに目立ちすぎるというリスクがある。だがこの際贅沢は言っていられないのだ。坂井からは毎日催促の電話がじゃんじゃんかかってくるし、スパイ志願の応募者ときたら、毎度お馴染みのぷっつん野郎ばかり。その上あの謎の中国女が面倒な仕事を増やしてくれたせいで、図太い中川も衰弱気味なのである。
「群島プロムナードにね、広告出してるんですけど……見ました?」
「広告ってスパイの募集だろう?」
「そうそう。あんたなら、できると思うよ。なんたってスパイの本場の生まれだし」
などと訳の分からない事を言いながら、中川はバナナ大福を勧め、出がらしの番茶を差し出した。
「スパイかあ……」
アーマスは早くも痺れはじめた足をもじもじさせながら手のひらの茶碗に視線を落とした。
「オー、ヒトバシラが立ってる」
「……? あ?」
「ヒトバシラが立つ。縁起がいいぜ、これは」
「茶柱ってんだよ」
「ハハハ……YOU、ニホンゴ詳しい」
照れかくしに、頭を掻きながら外人ぶりっこする。
(大丈夫かよ、こんな奴雇って……)
と、内心不安を抱かなかったと言えば嘘になる。
それでも、アーマスの人を警戒させない物腰は、スパイには適しているようにも思えた。
「プログラマーより高給なら、考えない事もないけどな。でも……うーん」
「茶柱も立ったことだし、決めちゃいましょうや、旦那」
「でも研修かなんかあるって書いてあっただろう……そういうの、面倒くさいんだよ」
「あんなもん、形だけのもんですって。まあ、これ読んで下さいよ。三日くらいかけてゆっくり読んでくれればいいから。楽なもんでしょ?」
そう言って、中川は本棚の奥から「スパイ大百科」と「月刊冒険少年/特別編集版・これで君もスパイになれる」の2冊を取り出してアーマスの前に突き出した。どちらも中川が幼少のみぎり、愛読した本である。愛読し過ぎてあちこちページが破れ、補修のために貼ったセロテープが黄色く変色していたりもする……見るからに年季の入った蔵書だった。
表紙を開くと「三年二組 中川かつみ」と鉛筆書きのへたくそな字で書かれているあたりが、なんともほのぼのとしている。
「もしかして……ひょっとすると研修ってこれのことかよ?」
アーマスは呆れて中川の顔を見つめた。
ともあれ……これで佐々木に送り込む最初の一人が決定した。
がちゃんっ! と乱暴にヴィジホンの受話器をフックに戻すと、真奈美は電話ボックスを出た。
「真由美のやつ、アタシのやることはなんだって馬鹿にするんだから! もう、ほんっとに可愛げない。でも、負けないからね。アタシ絶対にスパイをやるんだから!」
握り拳を元気に振り上げる。
その真奈美の目の前に……目指す『アブシンベル縁島』はあった。
「日下部真奈美ですっ! よろしくお願いします!」
猫のイラストが入ったピンク色の用紙に、グリーンのサインペン、判読困難なちまちまとした丸文字。にぱっと笑ってVサインという「3分でOK」のインスタント写真を貼りつけた履歴書をいきなり玄関口で差し出して、真奈美はぺこりと頭を下げた。尻尾のような長い三つ編みが、威勢のいいおじぎで跳ね上がった。
「……ゼロワンSTAFFの社長の、中川です。とりあえず、上がって下さい。話はそれからにしましょうよ」
そう言って、真奈美を部屋に上げる。
散らかり放題のワンルームの隅っこで、アーマスが「スパイ大百科」を読んでいる。小学生向けの本なのだが、しょっちゅう辞書を引くせいで、なかなか先に進まない。
「アーマス、悪いけど……それ、家で読んでくれるかな。二、三日持ってて構わないからさ。たぶんそのうち先方に挨拶にいく事になると思うから、時間、融通が効くようにしといてくれよ。今日の夜か、遅くとも明日の昼までには連絡入れるからさ」
そう言って、アーマスを追い出しにかかる。
オフィスが手狭だし、まだ登録するかどうか分からない応募者の面接で、プライバシーの問題もあるし……ともっともらしい理由はすぐに考えついたのだが、アーマスは何も言わずに腰を上げた。デイパックにさっきの本をしまうと、帰り仕度を始める。
もちろん、中川がアーマスを追い出すのは……日下部真奈美と名乗った応募者が可愛い女の子だったからだ。訪ねてきたのが野郎なら、そんな気を使ってやる道理はない。
そしてその中川の下心など、アーマスにはお見通しだった。
「よだれが垂れてるぜ、社長さん。商売ものに手を出すなよ」
「へっへ、それは言いっこなしだって」
にちゃにちゃと笑ってアーマスをこづく。
アーマスは呆れた表情を浮かべながらも黙って帰っていった。
「えーと、真奈美ちゃんだっけ? そこ座ってね。オフィスコンパニオンの募集広告見てきたの?」
急須の中のお茶っぱを入れ換えて、戸棚の中から出した茶碗に注ぎ、引き出しから新しい紙皿を探し出してバナナ大福を乗せる。
真奈美は座布団にちょこんと座って部屋の中をきょろきょろと見回した。
雑然とした中にチャン・リン・シャンの置いていったSD聖くんの縫いぐるみが投げ出されているのを見つけて、真奈美は腰を浮かせて拾い上げた。
「社長さんも、聖くんのファンなんですか?」
「いや……それはもらいもんでね。えーと、それで仕事の話なんだけど……」
「アタシ、スパイになりたいんですっ!」
「え?(^_^;)」
「スパイになって、活躍したいんです。あ、でも悪役はダメですよ。正義の味方でなくっちゃ」
そう言って、バナナ大福に手を伸ばす。
三口で平らげ、お茶もきれいに飲み干してしまう。ものおじという単語は、彼女の辞書にはないに違いない。……落丁である。
「スパイ募集の広告見てきたんだ……。うーん、美人スパイって言うにはちょっとバストが寂しいかな。(^_^)」
(……応募者は嬉しい。可愛い女の子も嬉しい……しかし……しかし、問題は……)
中川はさっき渡されたピンクの履歴書を調べた。
生年月日西暦2003年1月2日。
山羊座である。
いや、そんなことはこの際どうでもいい。
問題は年齢の方だ。
十六歳の少女を相手にするのは……もとい、雇うのは無理だった。
どう考えてもヤバすぎる。
「あのー、真奈美ちゃん? キミ、今なにやってるの。十六歳だったら、高校生じゃないの、もしかして」
「洋上大学付属高校の一年生です。あ、あと『まぐまぐバーガー』でバイトしてるんです。でもね、時給、安いんですよ。スパイだったら、もっとお金いいでしょ? だからここで雇ってもらえる事になったら、そっちは辞めようかなって。……あのー、アタシじゃ、ダメですか?」
「ダメっていうかね……うーん、困ったな。お父さんとか、お母さんは? ここに来てる事知ってるの?」
「うち、お父さんいないんです。お母さんにはナイショです。アタシ、家出してきたから……」
悪びれない笑顔でしゃらっと言ってのける。
「家出ね……家出……っと」
これで確実である。
雇えるわけはない。
いくら中川がちんぴら寸前のヤサグレ社長だとしても、世間を渡っていく以上やってはならない事がある。
家出中の未成年者をスパイとして使ったなんてことが表沙汰になったら、信用第一のこの稼業はそれっきりだ。下手をすれば後ろに手が回ることにも成りかねない。
「あのね、真奈美ちゃん。こうしよう。履歴書は預かっておくから、とりあえず家に帰りなさい。んで、四年ぐらい経ったら……」
「そんなのずるーい。そうだ、いいもの持ってきたんです。じゃーんっ! ね、まずは一杯やりましょっ☆ 話はそ・れ・か・ら!」
その言葉と同時に、真奈美と中川が膝を突き合わせている真ん中に、燦然と輝く一升瓶が置かれた。
(……またこのパターンかっ!)
思わず頭を抱えてしまう。
だが、逃げ腰の中川を、易々と逃がすような真奈美ではなかった。元辰巳芸者の母を持つ彼女の、3級宴会技能士免許(自称)は伊達ではない。
「社長さん、お酒好きでしょ? そんな顔しないで、陽気にやりましょ、陽気に。アタシね、スゴイ特技が有るんです。ほら、このコップ、お酒が一杯入ってるでしょ。種も仕掛もないんです。それでね、グビグビ、ほーら、あっという間にお酒は消えちゃいましたっ☆ はい、次は社長さんの番でーす」
とくとくとくとくとく。
「俺……酒に弱いから」
「早く飲まないとお酒こぼれちゃう」
「しょうがないなあ、グビグビ」
「すごーい、社長さん、強いじゃないですか。じゃあ、もう一杯、はい」
再び、とくとくとくとくとく。
茶碗になみなみとつがれた酒を飲み干してしまっては、煽て上手の真奈美の差し出す二杯目をを断る理性など、中川には残されていようはずもない。
「よしっ、おぢさんに任せなさい。今度はおぢさんの特技を見せて上げよう。この履歴書の生年月日のところをね、こうやってボールペンで……。グシャグシャグシャ。それでえーと、西暦1998年……と。うーん、ちょっとわざとらしいかな? でもまあいいっか。真奈美ちゃんはこれで21歳☆ ダイジョーブ、ちゃあんと雇って上げるから。真奈美ちゃん、正義の味方似合うと思うよ。スパイになって、活躍しよう。俺と一緒に悪の組織を叩き潰そうっ!!」
そこで記憶はぷっつりと途切れ、頭痛と後悔を抱え込んで目を覚ましたときには、中川の横で空になった一升瓶を抱えて、真奈美がすかすかと安らかな寝息を立てていた。
すでに夜は明けている。
スパイ志願の少女Aと一夜を共に過ごしてしまったのだが、もちろん泥酔状態の中川に悪さができようはずもない。
「母ちゃん、俺って……ダメな男かな……もしかして」
生年月日を書き換えたピンクの履歴を睨んで……中川は柄にもなく自己嫌悪に陥っていた。
「紀美枝お母さん、ここの味噌汁いつもうまいねえ。いい味噌使ってるんでしょう。実は俺、結構味噌にはうるさくってさ……。どこで買ってるのか、教えて欲しいんだけど」
なんて言う事を口にする食い道楽の連中が、紀美枝の紹介で『こうじや』を訪れるのだ。
「そうかぁ、ここ、味噌屋だったんだ」
という驚きの言葉を、彼らは大抵口にする。
毎日のように『味の屋』に足を運ぶような連中でも、『こうじや』と聞いて、
「ああ、『味の屋』の隣の味噌屋ね」
と、即座にぴんとくる人間は少ないに違いない。
構えが小さいのはもちろんだが、存在感が薄いというか、毎日見ていても印象に残らないのだ。それは『こうじや』だけでなく、坂井本人にも言える事だった。『味の屋』の常連客の中でも最古参と言えそうな坂井俊介を、いったい何人の「常連客」が覚えているだろう。
「坂井さん、何か心配事があるんじゃないんですか」
いつものように味噌を買いに来た杜沢と、食事でもしようということになって『味の屋』に入った。そのいちばん奥の席で顔を突き合わせているうちに、突然杜沢が坂井の顔を見つめてそんな事を言った。
杜沢跡見は、その数少ない『こうじや』の客のひとりだった。
まだ二十四歳という若さでありながら、洋上大学付属の博物館に勤め、キャリアこそ短いが遺跡調査の分野で確固たる実績を持つ……根っからの学者だった。仕事で外国に行くときにも必ず坂井の味噌を持参するという、『こうじや』のお得意様だ。
「うまいものを作る人間に悪党はいない」
そういう思いこみがあるせいか、坂井のことをいつもどこか買いかぶっている節がある。
「別に心配事なんて、ありません。私はいつもとあまり変わりませんよ」
鯵フライ&コロッケ定食の皿をつつきながら、坂井は微笑を作った。
杜沢は学者としての純粋な好奇心を抱き続けている男だった。遺跡調査に出かけた先の国々で、現地の住人と交流を持ち、時として事件に巻き込まれたりという波乱万丈の生き方をしてきた。
そんな中で鋭い直感とでも言うようなものを身に付けてきている。
坂井と顔を合わせるのは月に一度か二度、こうして味噌を買いに訪れるときだけなのだが、それでも以前会ったときに比べてその顔つきが険しくなっている。
口に出した事こそなかったが、これまでにも杜沢は坂井の素性に疑問を抱いていた。
流行らない味噌屋なんかやっているタイプの男とは思えないと感じていたのだ。何か心に秘めるものを持って、隠遁生活を余儀なくされているのではないかと薄々気づいていた。
「今……仕事がちょっと暇なんですよ。しばらく外国に出る予定もないし、骨休めと思ってすこしのんびりしようと思っているんです」
その言葉の裏には、協力するから打ち明けて下さい……という含みがあるように感じられた。
杜沢の右手の甲に刻み込まれた模様を見つめて、坂井は、彼に話してみようかとも考え始めていた。
彼はスパイとしての資質を秘めている。
外見からはあまり想像できないが格闘技を身に付けているし、何より遺跡発掘のために各国を回り、幾度となく身の危険に晒された事で培われてきた鋭い洞察力や判断力といったものがある。
「ある会社で社長さんが亡くなった。そして亡くなった社長さんのご長男がその跡を継ごうとしている。でもそうして欲しくはないと考えている人たちもいます。まだはっきりとは分からないが、社長さんはそういう人たちに殺された可能性もある」
坂井は声を低くして言った。
毎日のように電話をしているのだが、中川の返事は芳しくない。時間は余りないのだ。未知の人材を仕事に引き入れるのだから、ゼロワンSTAFFを経由しようが、『味の屋』でスカウトしようが負わねばならないリスクは変わらないだろう。
「殺人事件の究明ですか? 坂井さんが裏で探偵をしているとは知らなかった」
「殺人については……私の範疇じゃありません。私はそのご長男をね、確実に社長の座に座らせたいんです」
杜沢の顔がすっと引き締まった。
いつも通りの作った微笑の向こうにある、坂井の本心を見透かそうとその顔をまじまじと見つめる。
「――協力してくれますか、杜沢さん」
「今日はずいぶんお話が弾んでたみたいね、坂井さん。はい、冷や奴。珍しいのね、うちで飲むなんて。何かいい事でもあったんですか?」
杜沢の帰ったあと、ひとりでビールを飲んでいる坂井のところに追加注文の冷や奴の器を持ってきて、紀美枝は話しかけた。
「うん? そうだね。ちょっとね。こういう時は、家で一人で飲むのは惜しい気分だ。こうやって紀美枝ちゃんの顔を見て……」
天気があまりよくないせいか、客はいつもより少なかった。
だから紀美枝も手透きのようで、坂井の話にあいずちを打つ余裕がある。それがまた、坂井の上機嫌に拍車をかけていた。
『味の屋』の扉をがらりと開けて、若い学生を数名引き連れた男が入ってきたのはその時だった。
「をを! やはりこちらにいらっしゃいましたか。坂井さん」
バイオスフィア計画に代表される閉鎖環境下の農業、および農業心理研究などの分野ですでに知らぬ者はない存在。そして何より食品テロリストとして群島中に(多少誇張有り)その名を知られた男……。
白葉透がそこにいた。
「あなたに会いに来たのです、坂井さん。実は我が農業工学課で新種の大豆を開発したので、ぜひ坂井さんにもお目にかけようと……これで『こうじや』特製味噌を作って頂きたいものです」
実は先日、『味の屋』の女将である榊原紀美枝から、
「最近、坂井さん元気がなくて……。お仕事の事で何か悩んでいるみたいだわ」
……と小耳に挟んでいたのだ。
「坂井さんを元気づけるにはこれが一番!」
とばかりに今日の出動となった訳である。まあ、ふだん自分の家でやっている狂乱の宴会が、今日は『味の屋』に場を移しただけという話もあるが……。
年齢から言えば坂井の方が七、八歳上なのだが、この際それは関係ない。坂井の危機(大仰)を耳にして白葉はすっかり兄貴分……いや、どちらかと言えばお父さんの心境にいた。
「『こうじや』の未来について、味噌の秘めたる可能性について、今日はとことん話し合いましょう」
白葉はサンマ定食が運ばれてくるのを待ちきれずに、持参した紙袋をごとんとテーブルの上に乗せた。毎度お馴染み、農業工学部の『夜明け前』である。
「白葉さん、持ち込みはヤバイですよ」
だが、狼狽したのは坂井ひとりである。
酒が出ると同時に紀美枝がにこにこといつもの笑顔を浮かべてコップを運んでくる。
入ってきたとき、白葉の引き連れていたのは秘書と手近にいた2、3名だけだったのだが、
「白葉教授が『味の屋』で味噌についての特別講義をやります」
という携帯電話を使っての秘書の一言が、講義を聞きもらすまいとする熱心な学生たちをかき集めたことは言うまでもない。電話からほんの三十分と経たないうちに、学生を満載したトラックが『味の屋』に横付けし、二十名を越す人員が店内になだれ込むこととなった。
その光景たるや、ベトコンの襲撃か米騒動かと言うすさまじさである。
坂井はビールの瓶をはっしと抱きしめたまま、呆気に取られている。いつもながら、この連中のやることには驚かされる。
いったいこのバイタリティはどこから出てくるのだろうか。
「困ったわ、こんなにたくさんのお客さんがいらっしゃると思わなかったから……お味噌汁の具が……」
あっという間に開いている席はもちろん、床にまで座り込んで白葉と坂井をぐるりと囲んだ学生たちを見て、紀美枝はため息をもらした。すでに夕食時は過ぎている。早い日なら店じまいを始めようかという時間なのだ。
だが、この一団がそう簡単に腰を上げるとは思えないし、何より白葉と坂井が味噌の話で盛り上がろうというときに、味噌汁なしでは済むまい。
「ご心配なく」
そう言って、白葉はぱちりと指をならした。
学生の数人が背負っていたナップザックの中から大根と油揚げ、ついでに卵までを出して調理場に運び込んだ。
「えーとね。そう、味噌です。味噌と言うのは、非常に奥が深い。――例えば原料ですな。第2次世界大戦の物資不足で米や大豆が国家統制された後、長い長い混乱期をやっと抜け出た味噌は、もはや戦前のものとは全く別物になっていました。えーとですね、つまりはマスプロ……オートメ化してしまったんですな」
コップ酒をすすっている坂井にそうまくしたて、自分はまずは腹ごしらえとサンマ定食に箸を伸ばす。
「大量生産され速醸法で作られたり、バイオテクノロジーと称して一週間でできるようなすばらしい技術も生まれました。……が、ハーッ、おかげで画一的な味ばかりが一般へと普及してしまいました」
がっくりと頭を垂れ、コップの酒をぐいっと煽る。
「別に悪いってわけじゃありませんよ。……しかし、私は日本人のひとりとしてね、かすかな寂しさを覚えておるのですよ。坂井さん、それはあなたも同じでしょう」
「……ええ。その通りだ。まったく、その通りですよ、白葉さん」
力強く頷いて、坂井は白葉のコップになみなみと『夜明け前』を注いだ。手酌で自分のコップにも注ごうとしたとき、そばに座った学生が、さっと手を出して酌をしてくれた。
「添加物についても、昔の手作り味噌とは大違い。色をきれいにみせるために漂白剤とかビタミンB2を配合したり……それは努力と言えるものかもしれないが、私は悲しい。貧弱な味を補うために化学調味料を入れ、その上日持ちを良くするためにソルビン酸やらアルコールやら……嘆かわしい限りです。おまけに大豆は90%以上を輸入に頼りきり、挙げ句の果てには味噌の材料に脱脂大豆まで使われているのが現状です」
「ええ、まったくひどいものです。私の母は……名古屋の生まれでね。祖母から受け継いだ味噌がめで、自分で味噌を作ってました。スーパーで売ってる味噌なんか、ありゃあ味噌じゃない。味噌風味の化学調味料だって笑い飛ばしてたもんです」
「そこですよ、母から娘へ、娘からその子へ……代々受け継がれてきた味こそが、伝統と呼ぶにふさわしい絶妙のまろやかさを『こうじや』の味噌に与えているのです。私は断言しますよ。坂井さん、あなたの味噌こそ本物だ」
興奮して、コップ酒を口に運ぶピッチが次第に上がっている。
「いえいえ、私なんか、趣味がこうじてあの店をやっているだけです。ただ自分が、味噌が好きってだけですよ」
「いいや、そうじゃない。そうじゃないですよ、坂井さん。あなたは速醸法の味噌が氾濫するこの現代において、本物の味噌を頑固に伝える老舗の味を守り通しておられる。これは偉業と呼ぶにふさわしいものだ。趣味がこうじてなんぞというものじゃない。そこが偉いんだ、『こうじや』は」
ぐびっ。ぐびぐびぐびぐび。
「厳選した材料を使い、昔ながらの天然醸造法でじっくりと時間をかけて。本物の味と本物の香りを持つ味噌に仕上げる。……このひたむきで前向きな姿勢にこそ、違いの分かる消費者はこだわるのです! 蒸し煮した米や麦に麹菌をつけ、33〜35度で三日間、適度な、しかして微妙な湿気を与えて味噌用の麹を作る。大変な事ですよ、これは。さらに蒸し煮した大豆をくわえて、自然塩を良く混ぜて大豆を潰すわけです。しかもミキサーに入れてスイッチを押すだけじゃない。汗水たらして自らの力で大豆を潰す坂井さんの姿に、私は涙を禁じ得なかった」
酒のピッチはさらに早くなっていた。
すでに坂井でさえ、白葉の弁舌に押しまくられている。そんな中で学生たちには言葉を差し挟む余裕などあるわけはなかった。要点をメモし、味噌汁と酒を飲み、かっぱかっぱとコップを干す白葉と坂井につぎつぎに酌をする。それだけで精いっぱいだった。
「そして……えーとですな。樽にいれて熟成させるんですが、土用前に一度、樽の底まで空気を入れる『切り返し』を行うわけですな。20日ほどで作られる味噌が主流となっている中で、一年が食べごろという味噌へのこだわり……ああ、私はこの感動を押さえる事などできません!」
ぐびぐびっ。
「味噌1gの中に、百万個もの酵母が生きている!」
ぐびぐぐぐぐっ!
「なんと感動的な出会い、何というすばらしい真実!!!」
ぐぐぐぐぐっぐびっ!
「これぞ、愛です! 愛のなせる業ですっ! ……きっと坂井さんは、毎晩味噌樽を抱いて寝ているに違いないっ!」
ぐっ……!
「ん……? 何という事だ、コップが空ではないか」
「そうです、そうなんですよ、白葉さん。私は嬉しい」
酒をつごうとした学生から酒瓶をひったくるようにして取ると、坂井は握りしめた白葉のコップに自分で酒をついだ。
「白葉さんも農作物を汗水たらして作っておられる。だからこそ……だからこそ分かっていただけるのだと思います。そうです、愛、愛なんです。白葉さんの畑から頂いた輝く宝石のような美しい大豆を、私の手で一人前の味噌に育て上げる。それこそ愛と呼ぶにふさわしい感動です。私には子供はおりませんが、幼子に手を掛け、ふれあいながら育て上げる生涯をかけた事業にも通じる達成感。充実感があるではありませんか! 味噌はね、息子や娘も同然なんです。だから、ふらりと店に寄った、一見の客には売りません。味噌のためにわざわざ出向いて下さるようなお客様にこそ、私の味噌を食べて欲しいんです。私の味噌を愛してくれるお客様は、息子の嫁、娘婿も同然の存在です。大切にしなければならない。そう思うからこそ、また今年も立派な味噌を育てなければ、と自分自身を奮起させる事ができるんです」
坂井の言葉は、次第に白葉のそれに感化されつつあった。
そしてその狂宴はまさにたけなわを迎えようとしている。
そして、帰宅した坂井を、四畳半の座敷に転がっていた中川が出迎えた。
「来てたんですか。隣にいたんですよ」
「知ってるよ、良く聞こえた。ひでえ騒音公害だ。……それにしても、鍵くらいかけとけよな。いくら盗むもん何にもねえからって、不用心にもほどがあるぜ」
「こんなトコに上がり込もうなんて物好き……あなたくらいしかいませんよ。で? 集まりましたか、スパイさんは」
「ああ、とりあえず二人だけどな」
中川はそう言って立ち上がった。ペンダントライトの紐にくくりつけたマスコット人形が、こつんと中川の頭にぶつかった。
「邪魔くせえな」
そう言って、マスコット人形に軽く拳を当てる。
「あっ! うちの聖くんに何をするんです」
「………………ひじり?」
改めてマスコット人形を見る。
あの謎の中国女チャン・リン・シャンが持ってきたのと同じ人形だった。
「そう聞くと、ますます殴りたくなってくる」
「やめなさい。これは私のバースディ・プレゼントにと、隣の奈緒美ちゃんが……」
「いい歳して何が隣のナオミちゃんだ。助平爺いめ」
「放って置いて下さい。あの親子は私の……寂しいやもめ暮らしを送る私の、ささやかな心のオアシスなんです」
「そうかいそうかい、オアシスかい。親指シフトとは大したもんだ。ええいっ、何もしないからもう放せっ!」
本気で羽交い締めにする坂井をなんとか振り払うと、中川は擦り切れた畳にどかっと腰を降ろした。
「あんたって、どこまで本気かよく分からねえ男だよ」
「私はいつだってどこまでも本気な男です。真摯な生き方こそ私の目指す……」
「よくまあそういう根も葉もない事を立て板に水がごとく言えるんだ。おテント様に申し訳ねえとは思わないのか」
「それで、どんな人なんです。応募者のスパイってのは」
「これだよ」
そう言って、中川は茶封筒に入れた履歴書を差し出した。
「最初っからそうすりゃあいいんですよ。まったく素直じゃないんだから」
「あんたの顔見てると、日頃溜まってるフラストレーションが暴発するんだよ」
「フラストレーションため込むほどつつましい生活してやしないじゃないですか。やりたい放題、好き放題の……」
言いながら、坂井は封筒の中から履歴書を取りだした。
「中川さん」
「……(^^;)」
「なんですか、これは」
「………………リレキショ」
方や英語と日本語のちゃんぽん、方やピンクに丸文字。しかも丸文字の方は、鼻くそをほじりながら左足で書いたような中川の文字でわざとらしい修正が加えられているが、まだ十六歳の女の子なのだ。
Vサインの写真を見るに至って、貧血でふらりと倒れそうな衝撃を覚えた。
「どうしてもスマキになって運河に浮かびたいようですね、あなたは」
「待て待て待てって。人を見かけで判断するなんてあんたらしくないぜ」
「使える人材だと言うんですね? あなたの首を賭けてもそう断言できると?」
「……う、うん。(^^;)」
「素直なあなたはどうも信用できない」
「年寄りは疑いっぽくていけねえよ。素直になれの、素直じゃダメだの。そんな事言ってっとなあ、隣の後家さんにあんたが自白剤入りの五平餅食わせたこと、チクるぞ」
「じゃあちょっと、拝見しましょうかね。やはり人間、見た目より内容が重要ですよ」
「…………そういうやつだよ、あんたって。善人面して、美味しいトコつまんでさ」
だが、もはや履歴書に視線を落としている坂井は、中川の泣き言などには構ってくれなかった。
「アーマス・グレブリー……ふんふん、彼をプログラマーとして佐々木建設に送り込むと言うのも手かもしれませんね。問題はこっちの…………日下部真奈美?」
坂井は丸文字の履歴書を見て素っ頓狂な声を上げた。
それから、まじまじと真奈美の写真を見つめる。
「知り合い?」
「……」
「……おっさん」
「………………まさか……いや、そんなことが……」
「おおお――――い」
「だが……確かに面影が」
「殴るぞ、禿親父」
「全部聞こえてるんですよ」
「そんならそういう面してろよ。真奈美ちゃんがどうかしたの」
「いえ、何でも有りません。そうですね、明後日にでもこの二人を連れてきて下さい。詳しい打ち合わせをしましょう。あなたも、もちろん同席願いますよ。なんと言っても人手が足りませんからね。調達できない分は身体で払って頂かないと……。義一さんから、昨日電話を頂きましてね。社内の不穏分子がほぼ特定できたと。あと、佐々木建設のバイオスフィア計画に反感を抱いている企業と、環境保護団体がいくつか。中でも動きが活発なのが、ディア・グルッペ・シュペーアっていう外資系の……」
「DGS?」
今度は、中川が声を上げる番だった。
チャン・リン・シャンの顔がふっと浮かび上がる。
あの時に中川の感じた疑惑は、やはり気のせいなどではなかったのだ。
「何か?」
「ハハハハ……、何でもない」
「中川さん。私がちょっと口を滑らせれば、あなたはスマキになって運河に浮かぶか、コンクリート詰めで東京湾の底なんですよ」
「勘弁してよー。まだそのDGSが犯人って決まった訳じゃないんだろ。俺だって信用第一の商売やってるんだからさぁ」
「DGSに企業内スパイを派遣してるんじゃないでしょうね、ウチを差し置いて」
「そんな生命知らずな真似が俺にできるわけないだろ。受付嬢だよ、受付嬢。それにまだ依頼を受けただけで派遣してはいないし……」
慌てふためく中川の様子を見れば、それが嘘ではなさそうなのは分かる。
だが、いったいどういう事なのだろうか。DGSと言えば……佐々木建設などとは比べものにならない大企業だ。世界各国に支局を置き、それぞれの国で経済界の顔役としてのさばっている。そんな企業が、ゼロワンSTAFFのような極小零細企業を相手にするなど、あまりにも不自然だった。
「とりあえず、そのことも含めて検討しましょう。では明後日、ここで」
義一に会わなければならないと思った。
会って、真奈美の事を話さなければならない……と。
そして『こうじや』を出た中川も真奈美の事を考えていた。
考えると……頭が痛い。家出してきた泊まる当てもないという真奈美が、今もマンションの部屋にいるからだ。
可愛い女の子との同居。
やる事さえやれてしまえばそれはそれで極楽天国パラダイスってもんだが、相手が十六歳ではそうもいかない。その上真奈美は元辰巳芸者の母じこみのごまかし上手で、中川のアプローチをするするとかわしてしまう。なうての女たらしもお手上げの状態だった。
結局、ロフト部分を明け渡してやり、昨日も結局固い床に毛布を敷いて眠った。
そして真奈美の落ちつく先をなんとかしてやらない事には……部屋に女を連れ込む事もできない。
「俺って……俺って……こんなに面倒見のいい性格じゃなかったはずなのに」
頭痛は収まっても、自己嫌悪の方はまだ続いていた。
「乗って下さい」
絹のようなつややかな黒髪をきっちりとショートボブに切りそろえ、胸元を大きくみせるグレイのソフトスーツに身を包んだ女が、メタリックオレンジのコルベットカブリオレから顔を出した。型は古いが、隅々まで完全に手を入れて、現在広く出回っているスポーツカーと比べても遜色のない出来に仕上がっている。
義一はコルベットのナビシートに入り、ハンドルを握る真砂美に目をやった。
確か直に四十に手が届く年齢のはずだが、外見は二十代と言っても通用しそうな若々しさがあった。
「とりあえず、少し飛ばしましょう」
そう言うなり、真砂美はアクセルを踏み込んだ。
「どういうご用件かしら?」
「深川でブティックをやっているそうだな」
「ええ。――社長のニュースはテレビで拝見しましたわ。義一さん、その事でいらしたんでしょう?」
なかなか用件を切り出せずにいる義一に苛立ったように、日下部真砂美は話題を切り替えた。
「ああ……」
「奥様にご迷惑がかかると行けないと思って、お葬式は遠慮させていただいたんです」
「娘がいるとは知らなかったな」
「……」
真砂美は巧みなハンドルさばきで次々に前を行く車を抜いていく。
「戸籍も調べたが、認知していない。ひょんなことから真奈美って方の娘のことが分かって……それで一度会っておこうと思ってね。もう一人の娘は、まだ中学生だって言うじゃないか」
「興味、ありますか?」
「当たり前だろう、私にとっても妹なんだから」
真砂美は答えなかった。
娘の真奈美が洋上大学の付属高校へ進学するという話を聞いたときから、ぼんやりとこんな光景を予想していたような気がする。
真奈美にも、次女の真由美にも……父親の事は話したことがなかった。
だが真奈美は自分でも意識しないうちに、父の……辰樹のいる場所へ近づこうとしていた。
「少ないが……とりあえずこれを預けておく。財産分与の話が出るのはまだ少し時間がかかるんでな。君と娘のことも弁護士にちゃんとするように伝えておく」
義一は金の入った封筒をダッシュボードに置いた。
三百万円の現金が入っている。
「いりませんわ。財産分与も……私たちには必要のないものですから」
「だが……」
「頂くものは、もう社長から全部頂いてますもの」
それは、聞いている義一の方が辛くなるような……さばさばとした諦めきった口調だった。
「真奈美にお会いになったんですか?」
「いや……人づてに聞いただけだ。直に会う事になるだろうが……」
「あの娘、今家出しているんです。帰宅時間が遅いのを叱ったら、へそを曲げてしまって……」
「家に戻るように仕向けておくよ」
「放って置いても大丈夫ですよ。あの娘だってもう子供じゃないんだし」
その真砂美の言葉は、私たち家族の事には構わないで欲しい……と言っているようでもあった。
十六年、女手ひとつで二人の娘を育ててきた彼女の強さがその言葉には込められていたのかも知れない。
父親ほども歳の離れた辰樹の愛人となり、芸者からブティックのオーナーにまでのし上がったしたたかさは、その表情からは感じとる事はできなかった。
気丈な女……。
それが義一の抱いた印象だった。
いずれにせよ……いかにも父の惚れそうな女だった。
「また……連絡する」
待ち合わせに使った荒川べりの駐車場に真砂美のコルベットが戻ってきたのは、小一時間ほどのドライブを楽しんだあとだった。さっきまでは晴れていたのに、急に立ちこめた雲から大粒の雨が降り始めていた。
「副社長、東洋鉄鋼の岸田様が本社でお待ちになっています。すぐにお戻り頂けますか?」
停車中の車から高槻が走ってきて義一に傘を差し出す。その義一の身体から、微かに香水の残り香がたち昇った。
タイヤを鳴らして駐車場から出ていくコルベットを、二人の視線が見送った。
(副社長の愛人だろうか……?)
運転席にちらりと見えた女を、高槻はそう誤解した。
突然用立てることになったあの三百万円も彼女のところへ流れたのだろう。
(佐々木義一は愛妻家だと聞いていたが……しょせんこんなものか……)
スーツが濡れないように気を使いながら車に戻った。
バックシートでは義一のボディガードとなったハインリヒ・フォン・マイヤーが腕組みをしてぼんやりと宙を睨んでいた。
「これが……秘密基地かよ?」
卓袱台の上にボンベ式のガス焜炉が置かれ、その上でおでんがくつくつ煮えているのを見て、アーマスはこめかみをぴくぴくいわせながら中川を振り返った。
「……うん(^^;)」
「え――、でもでも、きっと床下にヒミツの地下室があったりして、ボタンひとつでぐい――んって巨大ロボットが出てきたり、飛行機が発進したりするんでしょ?」
真奈美が口を挟んだ。
もちろん、そんな仕掛があるわけはない。
だが、そういう話を間に受け易いやつは、どこにでもいるものだ。
「……そこかっ!」
いちばん奥の畳の縁が何度もそこに手を差し入れて、畳を上げましたといわんばかりにすり減っているのをめざとく見つけて、アーマスがどたどたと歩み寄った。
「畳返しだっ!」
中川の貸した本の中に、その技が載っていたのかどうかは謎である。
だが、アーマスの一撃で畳は見事に持ち上がった。
「ああっ、おでんの鍋が!!」
「いや――ん、すごい埃っ!」
「何をするんです、そこは……」
上から順に杜沢、真奈美、坂井がとっさにもらした言葉である。
中川は一瞬早く店舗となっている土間の方へ避難して何を逃れた。こういう……普段はぼさっとしている癖に土壇場でだけ逃げ足の早い奴は実在する。
「地下秘密基地への抜け穴だっ!」
歓喜の声が上がる。
だが、アーマスのその声はすぐに落胆の色を濃くした。
「……壷みたいなのがあるだけで、行き止まりみたいだな」
別にギャグをかまそうとか、受けを狙っているとかそういうことではない。アーマスはどこまでも真面目なのだ。
「そこは私が古い味噌がめをしまっているところで……ああっ覗かないで下さい」
という坂井の声が上がったときには、さっさと土間へ逃げていたはずの中川が、床下の穴ぐらをのぞき込んでいた。
「なんだこれ、ひぇえええええ、この結婚写真、坂井さんの? こ、これ奥さん? 美人――、勿体ねえ。あたら若い身の上でこんな助平爺いに……」
「中川さん、私だってその頃は若かったんですよ」
「えーと、こっちは預金通帳に、あ、社長、ビデオテープもありますよ。ずいぶん大きいですけど」
中川の横で、真奈美が歓声を上げる。
もうすっかり、中川のペースに馴らされているところがひたすら恐い。
「VHSのテープなんて骨董品を、今時持っている奴がいるとは思わなかった。アダルトかな? あ! 奥の方にテレビとデッキもある」
「何でそんなところにアダルトビデオなんか隠さなくっちゃいけないんですか。ママの目が恐い気弱な高校生でもあるまいし……。さあ、もうそんなところ、片づけて下さい。押入に入りきらないがらくたをしまってあるだけなんですから」
そう言って、彼らの詮索を何とか押しとどめる。
がらくた……と坂井は言ったが、どちらかと言えば床下は彼の「宝物の隠し場所」だった。
隠密として、身の上を隠すために処分しなければならなかったもの……だが処分しきれなかったものをこうして床下に隠してあるのだ。
時折畳を上げて、それを眺めているだろうことは……その縁の擦り切れ具合を見れば一目瞭然である。
「えー、ではですね。佐々木建設隠密チームの……なんか、しまらないネーミングですね。まるで家族対抗歌合戦だ。……まあ名前の事はおいおい考えましょう。正義の味方ササキ5ってのもいいかもしれませんね。まあとりあえず、その結成を祝して、そして親睦を深めるという意味で……うーん、ちょっとクラブ活動みたいですが、とにかく一席儲けさせて頂きました。あ、真奈美くん、中川さんにお酒を勧めないように。今日はとりあえず楽しんで頂いて、明日からはみっちり働いてもらおうという、そういう事です。佐々木義一氏が社長に就任した暁には、もっと豪勢な場所で祝杯を上げる事もできるでしょう。そのためにも頑張って下さい、みなさん。……はいはい、中川さん、あなたはジュースを飲んでてくださいね。まあ、堅苦しい挨拶はこれくらいにしましょう。おでんはまだお代わりもありますから、たくさん食べて下さい」
玉杓子をマイクに見立てて坂井が挨拶を済ませると、全員の箸が一気に鍋に襲いかかった。ひとり、箸に不慣れなアーマスが遅れをとってしまう。
「でさあ、坂井さん。俺思ったんだけどさ、脅迫状を出した奴の事はこっちでも調べがつくだろうけど、義一の旦那はどうすんだよ。生命狙われてるってのに、放っといていいの」
大根をかじりながら、中川が真面目な顔で言った。
「それは大丈夫です。元傭兵だったという男をボディガードに雇ったそうですから。私たちの動きから敵の目を反らすための意味もあるんでしょうね、軍事学部の講師だとかで、目立つ男でしたから」
坂井は味噌だれをたっぷりつけたこんにゃくを、ふうふう言いながら口へ運ぶ。
真奈美の事を告げるために無理を言って義一に会ったとき、高槻という若い秘書と、ボディガードとして雇った元傭兵、ハインリヒ・フォン・マイヤーを見かけたのだった。
義一は彼を雇った理由を何も語らなかったが、坂井たちの動きから敵の目を反らすための存在なのだろうということは一目で分かった。
確かに彼は優秀な人材なのだろう。そうでなければ、義一が目をつけるはずはない。
だが、それだけではないはずだった。
囮として使えるだけの目立つ男……。その条件を義一が見逃したとは思えなかった。坂井が見る以上、マイヤーは囮に使うには最適の存在だった。
「ごめんくださ――――いっ!」
その時、がらがらとガラス戸を開けて、店に入ってくる人の声があった。
「はいはい。お味噌ですか?」
すでに暖簾は降ろしてあったのだが、坂井は印半纏を掴んで立ち上がった。
その声になんだか聞き覚えがあるような気がして、中川も土間の方を覗く。
坂井が店の電気をつけた。
そしてその時……明るくなった土間に立っている迷彩タンクトップに赤いサスペンダーの少女を見て、坂井と中川は同時に声を上げた。
「……北海、珍味娘」
そうである。彼女こそかつて坂井に貝紐1キログラム入りパックを押し売り、中川のマンションの玄関口で延々三十分も「幸せの踊り」を踊り狂った……北海珍味娘こと森沢香南だった。
「なにしに来た。……待てっ! 食品サンプルを出すんじゃねえぞ。帆立て貝柱の話なんかするな。動くなよ……踊ったらぶち殺すぞ」
はんぺんを突き刺した箸を手に掴んだまま中川は土間に降り、すごみを効かせた。
だがその鼻先に、香南は指を突き出してチッ、チッ、チッと舌を鳴らした。
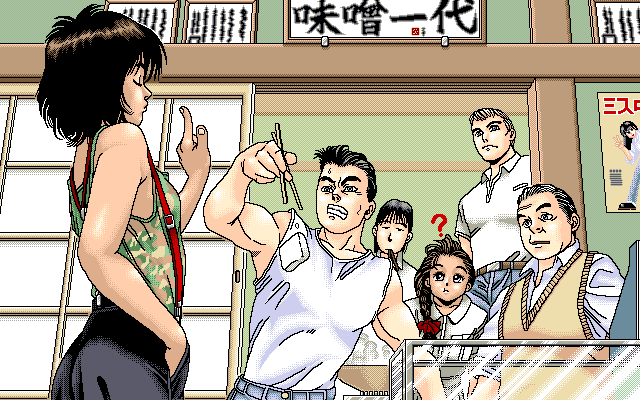
「香南、坂井ちゃんに用があってきたんだけど」
「さ……坂井……ちゃん?」
そう言って、中川と坂井は顔を見合わせた。
「私の……事ですかね」
「もっちろん。あのね、香南、佐々木のよっちゃんに頼まれて来たの。これから香南が連絡係をやるからねっ!」
さ――――っと血の気が引くのを、中川も……そして坂井も感じていた。
森沢香南が連絡係。
あの、北海珍味娘が……こともあろうに「連絡係」
いや、それはまあいい。
彼女ならこの群島のありとあらゆる場所に、怪しまれずに入り込んでいく事ができる。いや、もともと充分に怪しまれているんだって話もあるが……。
だが、いったい義一と彼女がどうやって接触したと言うのだろうか……?
佐々木建設の副社長室まで押し掛けていってスポーツバッグから食品サンプルを出し、「幸せの踊り」を踊って干し海老やのしイカを売りつける香南の姿が、総天然色、フィルターなしで思い浮かんだ。
中川の脳裏にも……。
坂井の脳裏にもだ。
信じたくない。
……信じたくはないが、ありそうな話ってところが恐い。
そして、急に『佐々木義一を社長さんにしちゃおう作戦(仮)』の行く末が不安になった。
土間にへたりこんだまま、中川も坂井もなかなかおでんを囲む宴会には戻って行く事ができなかった。もちろん座敷には、三秒でその場に馴染んでしまった、森沢香南の姿がある。