
Illustration by Kunio Aoki
「就業中の面会はご遠慮下さい」
の、一言で片づけられてしまった。
挙げ句の果てに警備部の連中に引きずり出される羽目となった。
(俺って……情けねえ……)
がっくりと肩を落としてマンションの部屋に帰ってくる。
実際、あの時中川が伊島プリンスに乗り込んで行ったからと言って、どうなるものでもなかったのだが、何もできなかった事が悔やまれてならない。
真奈美にあんな目立つ行動を取らせるというのは予定外の事態だった。佐々木建設の重役連中はあのニュースを何度でも見るだろう。
真奈美をスパイとして使う上で、こんな形で顔を知られてしまうというのは大きな誤算だった。
マンションの部屋の前には、一匹の白い猿が……中川の帰りを待っていたかのようにちょこんと座っていた。
「ぼくはすぱいになろう。すぱいになって、せいぎのみかたとしてだいかつやくすることこそ、ぼくにかせられたしめいなんだ」
……という、熱い意志を胸に抱いた天才猿、アインシュタインである。
で、あるのだが、これから先どうやって真奈美を使って行くか……いや、敵陣にひとり送り込まれ、あんな記者会見なんかに担ぎ出されて不安に陥って帰宅するであろう真奈美に……いったいどういう言葉をかけてやればいいのだろう、と悩んでいる中川には、猿など目に入らない。
「こんにちわ。ぼくはすぱいになるためにやってきたあいんしゅたいんです」
というアインシュタインの挨拶も、中川には、
「ウキッ、ウキキッ」
……という猿の鳴き声にしか聞こえなかった。
当たり前である。
如何に天才アインシュタインと言えども、人間の言葉をしゃべることはできない。
「このマンション、ペット禁止だぞ。どこの馬鹿だ、猿なんか飼ってやがるのは」
そう苛立った声で言い放ち、アインシュタインをその場に残してさっさと部屋に入ってしまう。
「ウキキッ(あぷろーちのしかたがよくなかったのかな?)」
アインシュタインは、小首を傾げて悩んだ。
「ウキッ! ウキキキキッ!(そうか! これはぼくがすぱいとしてかつやくできるかどうかをためすにんたいりょくのてすとなんだな。それならぼくはまけない。りっぱなすぱいになるまで、ここでがんばるぞ!)」
もちろん、中川にはそんな意図はない。
単にアインシュタインのことが眼中にないだけである。
その日、真奈美が帰ってきたのは午後九時過ぎだった。
一升瓶を抱え、猿を抱いてのご帰還である。
「真奈美っ、どこ行ってたんだ。七時過ぎにDGSに電話入れたらもう帰ったと……おまえ、酒臭いぞ」
「社長さん、ホテルと会社に来てくれたんでしょう? 奈美ねえ、うれしいっ。だから飲みましょっ! 今日の記者会見で特別ボーナスもらっちゃったんです。にじゅうまんえんっ。二十万円も! このお金どうしようかなって悩んだんですけどね。悪い人たちが悪いことして作ったお金でしょう? だからね、奈美と社長さんでね、これぜぇぇんぶ飲んじゃいましょっ。それがいちばんいいと思うの。正義の味方は悪いやつ、やっつけるんだもん。あーさん(注/杜沢のことである)とかグレさん(注/いわずもがなのアーマスである)とか……坂井のおじさんとか、香南とかね、みんなも呼びましょっ。奈美たち正義の味方だもんっ。全部、ちょっとも残さずのまなくっちゃ。ねえっ、社長さんも、ほら」
「とりあえず、みんなは他で戦ってるから。こいつは俺と真奈美で戦おう、な?」
そう言って中川はコップを出した。
とりあえず飲まずに収まるわけはない。悪の組織(まだ、「かもしれない」……の段階だが)の手先としてテレビに映ってしまった事が、よほどショックと見える。が、そう見える割に闘志に燃えている辺りはたくましい限りである。
「ふたりだけじゃないの。この子もね、一緒に飲むって。この子ねえ、アインシュタインって言うの。とってもお利口で、奈美の言う事、なあんでも分かるんだから!」
真奈美はまくしたてながら早いピッチで酒を開ける。中川にも、やや困惑気味のアインシュタインにもどんどん酒を勧める。
「ウキキッ!(これもすぱいになるためのしれんだ。ひっく!)」
「猿が酒を飲むとは知らなかった……」
「社長さん、何黄昏てるんですか? あ、おつまみにね、香南が会社に売りに来た北海の珍味があるんです。これ食べましょ? 社長さん、干し海老とイカの薫製、どっちがいいですか?」
「うーん、両方」
中川もすでにコップ三杯を開けている。
だがこの日は……先に酔いつぶれたのは真奈美の方だった。
眠り込んでしまった真奈美とアインシュタインに毛布をかけてやると、中川は車の鍵を掴んでおぼつかない足どりで部屋を出ていった。
「それで、泥酔して、車運転してウチに来たってわけですか。よく警察に捕まらなかったもんだ」
酔っているせいでどんよりと歪んでいる中川の視界に、坂井の顔があった。
「反省してます」
「真奈美くんの様子はどうなんです? もうスパイはやめる、とでも?」
「いや……記者会見の事はショックだったみたいだけど、逆にそれで燃え上がってるって感じだったな。DGS秘書課の……ウチに来た例の中国女が、明日の夜19号埋め立て地の白薔薇って店で華僑の大物の使者と会う事になっているらしいとか、結構いろいろ情報掴んでるみたいだし……」
「19号埋め立て地とはまた……穏やかじゃありませんね」
坂井は思わずため息をもらした。
人工群島の暗黒街とも噂されている治安の悪い場所なのだ。
「俺は面が割れてるし、アーマスにでも尾行させる積もりでいる」
「飲んでる割に、余り酔ってないみたいじゃないですか。珍しい事もあるものですね」
「酔えるもんかよ。こんな気分で」
「真奈美くんより、あなたの方が落ち込んでるみたいですね」
ぐったりと座り込んでいる中川に熱いほうじ茶を勧めて、坂井は笑った。
「テレビのニュース見た瞬間にさ。なんかこう……心臓わし掴みって感じがしたんだよなあ。真奈美が、助けてって呼んでるみたいな気がして。さっそうと現れて女の子を助け出すなんてのは俺、役得だと思うわけ。それであの時、それがやれると思った。……で、結局俺は渋滞に負けたんだよ」
「私にとっては渋滞はありがたかったですね。あんなところにあなたが飛び込んでいったのでは何もかもめちゃめちゃです。真奈美くんがスパイだとバラすようなものじゃないですか」
「そうかぁ……そうだよなあ。ぜんっぜん考えつかなかったよ、そんな事」
「余りうかつに動かないで下さいよ。DGSは得体の知れないところがありますからね」
畳に大の字に転がった中川に一枚しかないかけ布団を投げてやり、坂井は電気を消した。
西崎とDGSとの関係を早く調べなければならない、と坂井は考えていた。
その関係によっては、西崎は真奈美を利用しようとする可能性もある。真奈美の身に危険が及ぶ事も充分に考えられるのだ。
西崎が辰樹のかつての愛人の事を知らないわけがない。
あのニュースを見ていれば、西崎はすぐに真奈美の素性に気づくに違いなかった。
「急がなければ……」
そう、独り言を呟く坂井の声が、眠りに落ちようとする瞬間、中川の耳に届いた。
「隣の後家さんところに飯でも食いにいったかな?」
起きあがってアスピリンを水もなしに飲み下すと、布団をたたんで土間に降りた。
相変わらず、留守にしているというのに鍵もかけていなければ、暖簾も下ろしていない。そのくせ店の電気だけはしっかりと消えているところが謎と言えば謎だった。
「いらっしゃいませーーー」
中嶋千尋の声に迎えられて『味の屋』の店内に入った中川は、店の一番奥でテーブルを挟んで熱心に語り合っている坂井と、一人の男の姿を見つけた。
(……あの親父、確か『報道特番』に出てた)
中川はその姿を一目見ただけでそう気づいた。
白葉教授である。
『報道特番』では若い女の子を追いかけ回す変質者のようだった(……と、中川には感じられた)が、こうして見ると結構普通の中年である。
「お目覚めですか、中川さん」
「……おお、ちょうど今あなたの話をしていたところですよ。ええーーと、中川さんは人材派遣会社を経営しておられるとか」
「ええ、まあ」
そう言いながら、坂井の隣の椅子を引き出して座り、注文を取りに近付いてきた千尋に鳥唐揚げ定食を頼んで、コップの水を一気に飲み干す。
「何でも、オフィスでのお茶汲みを専門に取り扱っておられるとか?」
「一応コピー取ったりとか、書類の受け渡しとか……そういう事も業務に含まれてるんですが、まあ、仕事の大半は……そうですね、お茶汲みに精出してるみたいです」
「お茶……いいもんです。日本人の生活には欠かせないものですからな」
はああっと深くため息をつく。
そしてタイミングを見計らったかのように、千尋が三人の前にお茶を出した。
「?????」
呆気に取られているのは中川一人である。
すでに坂井は白葉のこういう突飛な行動にも、その行動にこうして絶妙のフォローを入れる千尋にも慣れていた。
「茶と言えば、まず茶の葉から見るなんて事も言いますが、しかしどんなに良質の葉を使っても、入れ方が悪ければ話にも何にもならないわけですな」
「は……はあ」
中川は圧倒されている。
そしてそれを横目にお茶をすすりながら、坂井は敢えて助け船を入れようとはしなかった。今日は何だか元気のない白葉が、中川相手に講義でもして元気を出してくれれば、と思ったし、それは中川の方にも言えた。
中川にいつまでもしょぼくれていられたんでは、仕事に差し支えるばかりか、坂井の楽しみも減るというものだ。
「一般家庭では……オフィスなどでもそうでしょうが、茶を入れるとなれば水道水を使う事になるわけです。水道水はまずいとよく言われますが、これにもちゃんとうまいやり方がありましてね。水をしばらく出しっぱなしにしてからヤカンに入れ、充分に沸騰させてやるわけです。こうすることによって、カルキ臭さが取れ、美味しいお茶を入れるための湯が出来上がるというわけです。……まあ、飲んでみて下さい。美味しいでしょう? 千尋には私が直々に教え込んでありますから」
言われるままに、中川はお茶をすすった。
……よく分からない。
味音痴なのである。
「はあ……。うまいです」
とりあえずはそう、口先だけで返事しておく。
「それで、えーとですな、さっぱりした味が好みでしたら、すぐにお湯を注ぐ。甘くコクのあるお茶にしたいなら、少し冷ましてゆっくりと出すと良い。ほうじ茶は煎茶の倍ほどの葉の量で、熱湯で短時間でケリをつける。これがコツです」
そう言って、白葉も千尋の入れたお茶をごくごくと飲んだ。
さすがに酒の時と違って、ピッチはそれほど早くない。
「お茶と一口に言っても奥の深いものでしてな。萌葱色の煎茶は食前、食後はほうじ茶が通の飲み方だとも言われます。まあ、さっぱりした煎茶で味覚を整え、甘味のあるほうじ茶で人心地つく……と、そういうことですかね」
もう一口、茶を含み、ゆっくりと味わってから飲み下す。
その表情は素面とは思えないほど恍惚としていた。
すでに中川は及び腰である。もちろん中川にはお茶に関する知識などひとかけらもない。玄米茶とほうじ茶なら何とか見分けがつかないでもない、というくらいのものなのだ。オフィスコンパニオンとして様々な企業に送り込んでいる女の子たちにもお茶の入れ方なんかをレクチャーしたことはない。
「煎茶で言うなら、やはり茶どころ藤川の『川根銘茶』でしょうな。お茶と言えば静岡県でしょうが、中でも中川根町藤川のお茶は、味、香り、外観と三拍子揃った最高級のものですな。大井川上流の山あいに位置する藤川の地は、肥料の吸着性の良い土壌、昼夜の寒暖差、川霧とお茶の栽培に適した自然条件を備えています。だからこそ、美味しいお茶が取れるのです。取り寄せてでも是非飲んでみたい逸品と言えますな」
茶碗に残ったお茶を、白葉は一気に煽った。
「いや、お茶は本当に健康にいい。ビタミンA……特にカロチンを多く含んでいる。まさに自然の恵みです。仕事に疲れたビジネスマンに一服の清涼剤とも言える日本茶をサービスする。すばらしい仕事ではありませんか」
「白葉さん……何か心配事でも?」
白葉の講義は、中川をたじろがせるほどの迫力だったが、それでも平素に比べればテンションが低いと言わざるを得なかった。それは単に、酒が入っていないから、というだけの事ではない。
そう気づいて坂井が口を挟んだ。
「いえ……仕事のことですよ。バイオスフィア計画の開発をお願いしていた建設会社の社長さんが、先日亡くなられまして。今後の展開がどうなるのか……いろいろと気になる動きもあって……」
その白葉の言葉に、中川の表情が僅かに動揺した。
が、その動揺を隠して運ばれてきた鳥唐揚げ定食に箸を伸ばす。
「実はウチの秘書の者に、内々に調べさせてみたりもしたんですがね。やはり社長という屋台骨を失うと企業はどうもバランスを崩すようで……。バイオスフィア計画に参入の意志を表明している……えーと、ですな。そうですDGSいう企業の動きも活発で、すでに大学に影響力を持つ代議士を抱き込んだとか抱き込もうとしているとか……嫌な噂もある。佐々木建設さんの株がどうのとか騒がれてますし、実験は遅々として進まない……いやもう、本当に頭の痛い事態で……」
白葉はそう言って、がっくりと頭を垂れた。
実際には、バイオスフィア計画の開発がどの企業によって行われようが、器として完全なものであれば大学側にとってはさしたる問題ではなかった。
だが、白葉はそうは考えていなかった。
生前の辰樹と幾度か会い、酒を飲んで話す機会をも持っていた白葉は、宇宙にホテルを建てたいという辰樹の夢に深く共感していたのだった。その夢が今後も受け継がれて行くならば、佐々木建設を計画に強く推したいと思っている。
宇宙ホテルを建てるという辰樹の夢には、いわゆる情熱のようなものがあった。
白葉も努力の人だから、分かるのである。
理想と努力と情熱だけで、白葉は今日の地位を築き上げた。だから、理想や情熱を持ち合わせない金銭主義には虫酸が走るのだ。
今の佐々木建設に、情熱があるのか……。
DGSに理想や夢があるか……。
白葉はそれを知りたかった。
「大胆ですね。……誰に見られているか分かりませんよ」
きっちりと七三に分けた石岡の髪には、僅かに白いものが混じり始めている。
四十一という年齢の割にその容貌は老け込んでおり……だが、目尻を下げてにやにやと笑う表情は、ひどく子供っぽい。
浩二はこの男が苦手だった。
普段はギャンブルに明け暮れる無能な男という印象を崩さないのに、こういう時に触れられたくないものを嗅ぎ出す能力には長けている。そして少しでも弱みを見せれば、死ぬまで食らいついてくるようなタイプだった。
「さっそく用件に入りましょう。浩二さん――とりあえずそう呼ばせてもらいますよ。神野って女の事でね、力になりたいんですよ」
「どこから嗅ぎつけてきたのか知りませんが、かかわり合いにならない方が身のためですよ」
「ご挨拶だな」
「神野という女に会った事を、最初から兄に話すべきだった。そうすれば、こういう事態にはならずにすんだはずです。兄ならきっと彼らの行動を押さえられた」
浩二は目を伏せて小さく息を吐いた。
神野麗子が広川書店というダミー会社を使って株を買い占め、そして一気に売りに出た。その結果として、株価は暴落した。
義一が記者会見のニュースを見て即座に対応に走ったため、DGSがもくろんでいたほどの打撃を佐々木建設に与える事はできなかったが、それでも防衛買いの為につぎ込んだ資金は安いものではない。
「兄なら……? 驚いたな、まさか本当に義一副社長に社長の座を明け渡す積もりだとは思わなかった」
「どういう意味です?」
「浩二さんはいい社長になると思いますよって……つまりそういうことですよ」
「DGSの傘下に下れ、とでも?」
「DGSをも見返してやるほうが楽しいですね」
「無茶を言う人だ。……ぼくにそんな力があるわけはない」
そう言って、浩二は立ち上がった。
伝票にすっと手を伸ばす。
「ぼくはね……あなたはある意味で義一副社長より有能だ、と思っているんですよ。ぼくと組みませんか。佐々木建設を嘗めてかかっているDGSに一矢報いたいとは思わないんですか」
「あなたはぼくを買いかぶりすぎていますよ。ここで話した事は忘れます。あなたも忘れた方がいいですよ」
それだけを言ってテーブルを離れた。
これで石岡が諦めてくれるとは思えない。だが、西崎や神野麗子のアプローチにそう対処したように、浩二には無関心でいる以外になす術はなかった。
喫茶店を出た浩二は、社には戻らず……そのまま地下鉄の駅へと向かった。
株暴落の後始末のために浩二以外の重役たちは奔走しているだろう。意見を求められる立場でない名ばかりの副社長が一、二時間姿を隠したところで困る者などいなかった。
浩二が訪れたのは洋上大学水産学部の試験場だった。
佐々木浩二は、洋上大学の卒業生である。在籍していたの経済学部だが、学部ごとの敷居が極めて低いこの大学の特性を利用して、水産学部に入り浸っていたのだ。卒業するのに五年もかかったのはそのせいだった。
今でもこの水産試験場にはよく出入りしている。
去年南米に出かけたときに連れ帰った魚を数匹預かってもらっているので、その魚たちを見に来る……というのが表向きの理由だったが、実際には仕事場にいるのが辛くなった時の逃げ場所と言った感じだった。
「やあ佐々木くん」
水槽の前にたたずむ浩二を見つけて、試験官である鈴木が近寄ってきた。人を案内している途中のようだった。
「どうも……また勝手に入り込んでいます。そちらは、新しい教授の方ですか?」
浩二は穏やかな笑顔を浮かべて、鈴木の後ろにいた男に目をやった。
痩身で、余り手入れのされていなさそうな髪をちょっと伸ばしている。ぼーっとしたように見える容貌だが、その男の目には、鋭い感性を秘めているのだと感じさせるものがあった。
「いや、博物館の館員をしている杜沢くんだ。今日はここの見学をしたいと言ってね。おお、そうだ。佐々木くん。もし時間があるのなら、君が彼を案内してくれないかね?
どうせここの事は私より君の方が詳しいくらいだし……若い同士で話も合うんじゃないかな。――あー、杜沢くん、この佐々木くんは、あの佐々木建設の社長の御曹司でな。先頃お父さんを不幸な事故で亡くされたんだが……。今は建設会社の副社長をしているという変わり種なんですよ。うちの学部の出身者じゃ一番の出世頭だ。そのくせ自分の水族館をこの群島に作るのが夢という……」
「試験官、電話ですーーー。農業工学部の白葉教授から!」
鈴木の話を遮るように、事務所の方から声が響いた。
「やれやれ、忙しい事だ。白葉くん、今度は何かな? ちょうどいい鯖が入っているからついでにあれを20キロばかり持って行ってもらおう。じゃあ、頼んだよ、佐々木くん」
呆然としている二人をその場に残して、鈴木はイボイボ健康サンダルをぺたくたいわせながら事務所へ走って行った。
その背中を見つめて、杜沢はくすっと笑いをもらした。つられたように、浩二の顔もほころぶ。
「魚、好きでいらっしゃるんですね」
会話を切り出そうと、杜沢の方から話しかけてみる。
佐々木浩二は、杜沢が考えていたよりずっとナイーブそうな男だった。
坂井に「協力する」と言った杜沢だったが、アーマスや真奈美が企業に潜入したような形でのスパイ活動をするつもりは最初からなかった。
もっと側面から攻めていこう。
それをする人間が必要だと思ったし、何より杜沢の性分に合っている。
義一の弟にあたる佐々木浩二に接触して、情報を収集すると共に、彼を社内の……そして社の外にいる不穏分子から――様々な意味で――守ること。
杜沢が坂井から頼まれたのは何よりもその点だった。
今は義一の部下のようになっている坂井だが、雇用主はあくまでも故辰樹である。だから義一を守るのと同じように、浩二を守らなければならなかった。
だが、浩二の側からは積極的なアプローチはなかった。
沈黙して、自らの胸中を語ろうとしない。
坂井にはそれをどうしても知らなければならなかった。浩二が何を考え、どう行動しようとしているのか……。
それを、杜沢に探ってもらいたかったのである。
坂井から浩二の話を聞くうちに、杜沢は佐々木浩二という男に深い関心を抱くようになった。
業界トップクラスの企業の副社長であり、望めば社長の地位に就くことも不可能ではない。そんな立場にいる浩二が、それらをすべて捨て、ゼロから水族館を作りたいなどと言っている。
スパイとしての仕事以前に、会ってみたい、と思わせる何かがあるのだ。
そして今日、公園でぼんやりと風に吹かれているうちに、この水産試験場に来る事を思いついた。そこに浩二が来る事を知っていたのではない。浩二の方も、今日ここに来る事を予定していた訳ではなかった。
杜沢は何となく今まで一度も行った事のない水産試験場に足を運んでみたくなり、そこでふらりと立ち寄った浩二に偶然出くわしたというわけだった。
こういう偶然を、杜沢はよく経験する。
「佐々木建設の社長が交通事故で亡くなった、というニュースはテレビで見ました。まだ働き盛りという印象の強い方だったそうですね」
水槽の間をゆっくりと歩きながら、杜沢と浩二は取り立てて意味のない世間話をしていた。そういう会話を、杜沢は少しずつ、巧みに辰樹の事にずらしていった。
「ええ。もう五十過ぎだったのに、枯れてないっていうか……。子供の頃に抱いた情熱にがむしゃらにしがみついているようなところのある人でしたから」
「そういう人を失うというのは……会社も、でしょうが……ご家族にとっても大きな打撃でしょう」
「そうですね……。でも今は父を失った事で会社がいろいろともめてましてね。それで家族にとっても悲しみは後回しって感じです。バイオスフィア計画、ご存知でしょう? あの計画はうちの会社が請け負っているんです。父の夢の、第一歩として。でもそれも……この先どうなるか。……父の夢はね、宇宙にホテルを建てる事だったんです。宇宙に、地上と同じようにくつろぐ事のできる空間を作り出す事が、宇宙開発の目指す最終的な段階だと、良く言っていました。その夢が……その夢を見ている父が、ぼくは好きでした。腹黒い開発屋と、世間からは決して評判の良くなかった父だったけれど、その夢を語るときの父は……なんて言うか……魅力的でした。そしてその同じ夢を、今は兄が抱いている。そういう意味ではぼくは鬼子だったのかも知れませんね。でもね、ぼくが佐々木建設を出て、水族館を作りたい、と感じているその思いのいちばん奥深い部分には……何もない宇宙に飛び出して行って名を上げたいっていう父の野心があるような気がするんです。その野心を受け継いだから……ぼくはこういう夢を抱いてるんじゃないかって。ずいぶんスケールは違いますけどね」
自嘲するように、浩二はだが柔らかい笑いをもらした。
「会社は、お兄さんが継がれるんですか」
「……」
浩二は何かを言おうとして、言葉を詰まらせた。
そして杜沢の顔を見つめた。
杜沢が信じるに値する人物かどうかを確かめたがっているような、そんな視線だった。
ひときわ大きい水槽の前で立ち止まり、浩二は杜沢を振り返った。
杜沢の質問にはまだ答えていないままだった。

「シュメル……メソポタミアの古名から?」
「ええ。ああ、そうだ杜沢さんは博物館の方でしたよね。ぼくより良くご存知のはずだ」
「紀元前三千年ごろ、人類最初の都市文明を発展させた……メソポタミアの古名であると同時にその民族をもさす言葉です。……ロマンチストですね、佐々木さんは」
「考古学にはあまり見識が深くないんですが、何となくこの名を聞くと、父のことが思い浮かぶんです。紀元前三千年……そんな昔にも父と同じ夢を抱いた人たちがいたんだなって。歴史の本には彼らの情熱までは書かれてはいなけれど……父を始めとして、たくさんの宇宙開発に携わる人たちが、その大昔に都市を造り、歴史を大きく変えていった人たちと同じ情熱を抱いてるんじゃないかって、そう感じるんです」
「日干し煉瓦で都市を造った人たちと……宇宙に都市を築こうとしている人たち……そうですね。似ているのかもしれない」
「このイルカが生まれたばかりの時、試験官や教授たちの目を盗んでね、水槽に入って一緒に泳いだんです。水族館を作りたい……例え父の望んだぼくの将来からははずれてしまうとしても、ぼくはそうしなければならないんだと感じたんです。父が自分の野心に生涯を捧げてしまったように……ぼくはぼくの夢を追うべきだって」
浩二の目はぼんやりと……水槽の中のイルカを見つめていた。
「どんなに憧れても、手の届かないものってあるでしょう。ぼくにとって父や兄はそういう存在なんです。でも、世の中ってままならないものです。あの交通事故が父の野心を奪い、その情熱故に兄を追っている。ぼくを傀儡に据えて父の描いた夢の上に楼閣を築こうとする者がいる。夢でもなく、情熱でもなく……金と権力のためにです」
その言葉は……表面上は穏やかなものだった。
しかし、杜沢はその奥に秘められた浩二の激しい憤りを感じとっていた。
金と権力。
それを盾に人を脅すやり口は、杜沢にとっても好きになれるものではなかった。
こうして話を聞くうちに杜沢は……義一のためではなく浩二の為に、卑劣な脅迫者を探り、その企てを阻止したいと考え始めていた。
義一を佐々木建設の社長に無事就任させる事……それこそが浩二を、彼がイルカと水槽の中で泳ぎながら抱いた夢に向かって突き進むための第一歩となるのだから。
まだ、浩二の夢はスタートラインに立つことさえできずにいる。
杜沢はそのスタートラインを引き、彼の地面を蹴って走り出す浩二を見つめる存在になりたいと感じた。
「……すみません、初対面のあなたにこんな話をしてしまって」
照れたように言って、浩二は頭を掻いた。
杜沢の人当たりのいい印象は、平素口数が少なく、聞き役に回る事の多い浩二を饒舌にしていた。
「いえ、いいんです。多いんですよ、こうして相談相手みたいに話を聞くことって。人畜無害そうに見えるんでしょうね。訴え仏でいるのが……分にあったことなのかもしれないし」
明け放たれたドアから吹き込んできた風が、杜沢の伸びすぎた前髪をばさっとなびかせた。それを押さえようとした彼の右手の甲に紋章の様なものが刻み込まれているのを見つめて、浩二は彼に話してみようか……という思いにかられていた。
これまで誰にも相談できずに悩み続けていた事……西崎やDGS、神野のことを。
彼なら……信じて打ち明けられるような……そんな気がしたのだ。
「杜沢さん、DGSという企業をご存知ですか……」
「杜沢さん、今日いらっしゃる事になってましたっけ?」
鍵が掛かっていないのをいい事にずかずかと座敷まで上がり込む中川とは違い、律儀に暖簾の下で声をかけて、杜沢は『こうじや』を訪ねてきた。
「いえ……あ、お忙しいなら出直しますけど。いい鯖をもらったんで、味噌煮でも作ろうかなって。ちょっと報告したい事もありましたし……」
「鯖の味噌煮ですか、いいですね。今日は邪魔者(注/無論、中川の事である)も来ないはずですし、二人で静かに飲みますか。実は今日農業工学部の白葉さんがまたいらっしゃいましてね。またお酒を頂いたんです」
「それはいいところに来たな(^_^)。じゃあ、ちょっと台所お借りします」
すでに勝手知ったる他人の家……である。
杜沢は味噌作りの時に使うためにいくつか置いて有る坂井のエプロンをつけると、裏の味噌工場の片隅にある台所に向かった。
「今日、佐々木浩二さんに会ったんです」
味噌煮に箸をつけながら、杜沢は言った。
杜沢がそんなに早く行動を起こすとは考えていなかったため、坂井の表情はちょっと意外そうなものだった。
「本社にいらっしゃったんですか」
「いえ……。水産学部に行ったときに偶然お会いしたんです。まったくの見知らぬ通行人として、無駄話をしたって感じですね。……でも収穫はいろいろありましたよ。全くの見知らぬ通行人だからこそ、話せることってのもあるでしょう? DGSの神野という女が、彼を訪ねてきたそうです。浩二さんは人を悪く言うのが苦手と見えてね、話しにくそうにしてましたけど、ずいぶん高飛車な女のようだ」
「驚いた人だな。……あの浩二さんから、初対面で良くそこまで聞き出せたもんだ。彼は……そうですね、私はほんの子供のときのことしか知らないんですが、感性が鋭くて……その感性の鋭さから内向的になってしまっているような……そんなタイプの人でしたから」
「彼の話を聞いてね。私は俄然やる気を出してるんですよ。浩二さんを利用して甘い汁を吸おうとしている連中に対してね……他人事とは言え腹が立ってたまらないんです。水に抱かれて夢を見たって彼はそう言っていました。建設会社の仕事をやめて……水族館を作りたいと、そう言っていました。その言葉通り、浩二さんの見てる夢って、誠実で、純粋なんだなって感じたんです。 俺ねえ、思うんですよ。ある意味では、浩二さんって義一さんよりずっと辰樹氏に似ているんじゃないんでしょうかね。義一さんは……お会いした事がないんで断言しちゃうのもどうかと思うんですけど、坂井さんの言葉から推察するとね、「優秀な二代目」って感じがするんです。辰樹氏の見た夢、抱いた野心、その情熱を受け継いでいく後継者だなって。でも……浩二さんは違う。彼もまた、辰樹氏がそうであったように「夢を生み出す」者なんです。俺、彼を守りたいと思ったんです。彼の夢をね。そのためには、彼を傀儡の座に押し込めようとしているDGSや重役の西崎とかっていう連中の野望を阻止しなければならない訳でしょう?」
これまで口に出した事はなくとも、坂井が佐々木兄弟に対して抱くのと同じ感触を、杜沢もまた抱いたのだ。
杜沢が、珍しく熱っぽく喋るのを聞きながら、坂井もまた、かつて自分が抱いた思いを……いや、今も抱き続けている思いがたぎってくるのを感じずにはいられなかった。
辰樹の抱いた情熱を守りたい。
その思いこそが、坂井を隠密たらしめる最大の要因だったのだから……。
「せめて宿代替わりに炊事洗濯掃除をやりまーす」
と言って、真奈美は家事に勤しんでいた。
「宿代なら、身体で払ってくれればいいのに……」
という中川の提案は、無言のままに却下されてしまった。(^^;)
しかし今日の片付き様はその真奈美の掃除ともひと味違うのである。キッチンの隅々まで丁寧に雑巾がけがされ、窓も電灯のシェードもきれいに拭かれている。
いくら頑張っているとはいえ、日常の掃除でそこまでするほど、真奈美はマメな女の子ではない。
「ウキキッ(しゃちょうさん、おそうじしておきました)」
アインシュタインは誇らしげに胸を張ってそう主張したのだが、中川がそれに気づくわけもない。
「おうっ、腹が減ったか。今飯にしてやるからな」
ダイニングのテーブルには、真奈美が作った朝食が置かれていた。ご飯に味噌汁、目玉焼き、といういつものメニューに加えて、茸のあんかけ、ほうれん草の白和えなんていう手の込んだ品も用意されている。
「真奈美の奴、酔いつぶれて人格が変わったのか……?」
テーブルの上には真奈美の相変わらず丸っこい字でメモも残されていたのだが、その字面だけを読んで、中川は屑篭に放り込んでしまった。
そのメモには、
『今日の朝ご飯、豪勢でしょ? なあんとアインシュタインが手伝ってくれたのっ! やっぱりこの子、天才じゃないかなあ。おさるさんにお料理ができるなんて、奈美、ぜんぜん知りませんでした。すごく美味しいから、食べて元気だしてね☆
奈美はこれから出社します。もう昨日みたいにぷっつんしないから、安心してね』
と、書かれていた。
中川が読んだのは主に最後の一行だけである。
「けなげないい子じゃねえか」
「ウキキッ(まなみちゃん、いいこだよ。ぼくもそうおもう。うんうん)」
「そうか、おまえもそう思うか」
意志が疎通しているように思えるかも知れないが、これは単なる偶然という奴である。
「この白和え、イケるなあ。ほら、おまえも食ってみろよ。真奈美がこんなに料理がうまいとは思わなかった」
「ウキキ!(まなみちゃんじゃないよ。このしらあえはぼくがつくったんだ)」
「そうか、うまいか? よしよし、猿にやるのも勿体ない気もするが、特別に分けてやろう」
そう言って小皿を出し、アインシュタインに取り分けてやる。
しかたなく、アインシュタインは勧められるままに白和えを食べる。これも試練だ、と考えたかどうかは……分からない。
「ウキキッ! (これみて、しゃちょうさん)」
きっとこの人は言葉が分からないんだ。文字で書けば分かってくれる。
そう考えてアインシュタインは新聞のチラシの裏にサインペンで大きく、
『しゃちょうさん、ぼくをすぱいにしてください。いちにんまえになるまではこうやってそうじをしたりごはんをつくったりします』
と書いてテーブルに乗せた。
中川が食事を終えて立ち上がったのはその時だった。
「さあーーーて、アーマスからの連絡が来ているはずだから、それを確認しなくちゃな」
もちろん、アインシュタインの書いたメモなど目に入っていない。
コンピュータの前に座ると、アーマスから届いているメイルを読み始めた。
「ウキキ!(しゃちょうさん、これみてください。ぼく、すぱいになりたいんだ)」
「悪いな、あとで遊んでやるから……。ほら、これやるからこいつに遊んでてもらえ」
面倒くさそうにそう言って、チャン・リン・シャンの置いていったSD聖くんの縫いぐるみをアインシュタインに投げる。
「ウキキ!(そうじゃないんだ。ひじりくんはしーたのともだちだけどいまはそれはかんけいないんだ。ぼくはすぱいになりたいんだ)」
が、それも虚しい抵抗だった。
広川書店についての情報に目を通している中川は、すでにアインシュタインのことなど忘れ去っている。
ここまでやると、なんだか可哀想でもある。
しかしアインシュタインは聖くんの縫いぐるみを抱きしめたまま、ちょこんと中川の机の上に座って大人しくなった。
(これもしれんだ。がんばろう。ウキキ)
知能だけでなく、忍耐力も人並……いや猿並外れたやつである。
天才アインシュタインの名は伊達ではない。(なんのこっちゃ)
そして、別に中川もアインシュタインに意地悪をしているわけではなかった。単に猿が天才で、人の言葉を解し、文字を書き、挙げ句に掃除をして料理にも堪能だなどということが中川の範疇から大きくはずれているだけのことだ。
「広川書店ってのはやっぱりDGSのダミー会社か」
中川には、こういう裏の情報を手に入れるためのいくつかのルートがあった。他の企業に根を下ろす人材派遣業界では、こうした情報は金さえ出せばいくらでも手に入れられるネットワークのようなものが出来上がっている。
玄関の呼び鈴が鳴ったのはその時だった。
「はい?」
「群島プロムナードの求人広告を見てきたんです」
呼びかけたインターホンから返ってきたのは若い女の声だった。
言葉のアクセントからすると、またしても外国人らしい。
「今ごろ、応募者が来るとは思わなかったな」
そう思いながら、中川は玄関の方へ歩いて行った。
プロムナードに広告を出したのはもう三週間も前の事だ。
そしていつもなら必ず覗き窓から相手を確認するのに、今日に限ってすぐにドアを開けてしまった。
開けてしまってから……海より深く後悔する。
そこに立っていたのは色鮮やかなサリーに身を包んだインド人だったからだ。
「ナマステ」
開口一番シータ・ラムは言った。
その一言だけで中川を床にヘタリ込ませるには充分すぎる威力を持っていた。
「と、とりあえず、中へどうぞ」
力の抜けた膝を、何とか起こして部屋の中へ案内する。
座布団を勧め、汚れた茶碗に番茶を注いで(白葉に聞かされたお茶の美味しい入れ方はすでに中川の記憶には残っていない)昨日スーパーの特売で買った葛桜と一緒に差し出す。
「あたし、スパイの美学に憧れてるんですっ!」
というシータの言葉が発せられたのはその時だった。
「スパイをやるには、それなりに恵まれた容姿っていうか……あたしが言うと嫌みに聞こえるかも知れませんけどぉ、整った外見って奴が必要だと思うんですよね」
だがシータの演技力はチャン・リン・シャンのそれには遠く及ばなかった。(^^;)
フローリングの床に「の」の字を書きながら、
「一回、二回、三回……四回……で、いいんだっけ?」
なんてもらす辺り、まだまだ若い。
その上、本人は「の」の字を書いている積もりなんだろうが、どっからどう見ても「α」の字を書いているようにしか見えない。
しかしそれでも、中川を再起不能に追い込むには事足りた。
おまえだって充分非常識な奴だよ、と言いたい人はいっぱいいると思う。あ、試しに手上げてみて下さい。うーん、やっぱり多いですねぇ。
向かいにへたりこんでいる中川を尻目に、シータの「太ったチャイナ女」ぶりっこはまだ続いている。
「あれ? なんかちょっと違うかな? こう……こうかな?」
「ぶち殺すぞ」
ようやく復活した中川にそうドスの効いた声ですごまれて、ようやくシータは顔を上げた。頭から血を吹きそうな中川の形相に、にっこりと無邪気そうな笑顔を向ける。
「だって、こうすれば話を聞いてくれるって、チャンに教わったから……」
「……チャン?」
「ご存知でしょ? チャン・リン……」
「言うな。頼む、言わないでくれ。話なら何でも聞いてやるから」
「昔むかし、あるところにおじいさんとおばあさんが……」
「…………おい」
「はい?」
「そんなヨタ話をするためにわざわざそんな仮装してやってきたのか」
「これ、仮装じゃなくて盛装なんですけど。それにヨタ話じゃなくて、これは日本の昔話の……」
「俺が言いたいのは、そういうことじゃないんだ」
「……」
「どういう用件で来たんだって、そう聞いてんだよ」
「会話の前に軽くジャブと思って冗談を飛ばしてみたんですが……受けなかったとは残念です」
「軽いジャブが致命傷になることだってある。そういうことだよ」
「異文化間の交流はなかなか難しいものがありますね(^_^)」
「それじゃあ何か? インドじゃ他人の家を訪問するときにはいちいち中国人の助言を求めて嫌がらせの算段を練ってるわけか?」
「まあそういきり立たずに……。とりあえずこれを。うちの社長のマスコット人形なんです。名刺代わりににお納めください。私はシータ・ラムって言います」
そう言って、シータはSD聖くんを差し出した。
――いわゆる、火に油を注ぐ行為というやつだ。
しかもライディングナイトのエンブレムのついた特製だった。
しかし、そんな事は中川には関係なかった。エンブレムがついていようがチキータバナナのシールがついていようが、金のエンゼルがついていようが、そんな事はどうでもいい。
「そんなに死にたいか。そんなに俺をインド人強姦殺人でブチ込みたいか。チャン・リン・シャンのやつ、いつか絶対に殺してやる!」
「まあまあ、そんなに喜ばないで」
「怒ってるんだっ!!」
ぜえぜえと肩で息をしながら、それでも何とか冷静を装って立ち上がり、滅多に吸わないタバコを引き出しの奥から探し出してくわえると、ガスレンジで火をつけて煙を吸い込む。
「用件を聞いてやる、聞いてやるから百文字以内で説明しろ」
一服して気を取り直したところで、中川はキッチンから戻ってきた。
短気な様でいて、実は結構つき合いのいい男なのかもしれない。
いや、単にこうやって女に玩具にされるのが好きなのだと言うハナシもある。所詮、根っからの女衒なのだ。
「貴社はスパイの派遣をなさっているそうですが、運び屋、逃がし屋の派遣はやっていただけませんか? つまり……当方の社長聖武士――仕事上はライディングナイトというコードネームを使っているんですが。その仕事を……」
突然、シータは黙った。
「……」
「……」
「どうした」
「百文字越えちゃったんですけど……」
「いいから続けろ」
「……捜して欲しいんです」
「あんたもやるの、その逃がし屋だか、運び屋だかを?」
「私は……まあマネージャーみたいなもんです。仕事をするのは社長の方です」
「つまり、あんたは自分の仕事を俺に押しつけたいと……そういうことだな?」
「……(^_^)\カリカリ」
「そういうヤバイ仕事はおおっぴらに集められないからな。あんまり宛にしてもらっても困るが……俺の取り分次第ってところだな。税金のかからない収入ってのは、俺も嫌いじゃない」
「そうですねえ、仕事の代金は大抵このくらい……カキカキ……もらってるんですが」
そう言って、
『しゃちょうさん、ぼくをすぱいにしてください。いちにんまえになるまではこうやってそうじをしたりごはんをつくったりします』
と書かれた例の新聞のチラシの隅っこの方に7桁の数字を書いた。
「紹介していただいた場合、ゼロワンSTAFFの取り分は、一割でどうでしょう?」
「まあ、妥当な線だな」
「じゃ、引き受けてくれます?」
「期待はしないでくれって言っただろう。そういう需要があれば電話する。番号は?」
「ここにメモしときますね。カキカキ。電話待ってます。首を長くして」
そう言って、シータ・ラムは立ち上がった。
座布団が薄かったせいで、ちょっと足が痺れている。
「あれ? アインシュタイン」
立ち上がったとき、机の上でなぜか座禅を組んでいるアインシュタインを見つけてシータは声を上げた。
ちょうどその時電話が鳴って、中川が席を外した。
「昨日っから見当たらないと思ったら、こんなところにいたの?」
そう呟いて、さっきメモ代わりに使ったチラシに書かれていた文字が、アインシュタインのものなのだと気づいた。
「スパイなんて危ない仕事はやめなさい」
アインシュタインはぱちっと目を開け、机の上に放り出してあったノートに、何やら書き始めた。
『じぶんのことをたなにあげてなにをいっているんだ。ぼくはすぱいになるためのしゅぎょうをしているんだから、じゃましないで』
そう書いて、再び座禅のポーズを取る。
「…………いいけどね、別に」
「……というわけで、仕事回してくれるように頼んできたわ」
突然聖武士の部屋に飛び込んで来て、シータ・ラムが言った。
「人材派遣ゼロワンSTAFFねえ。ホントに仕事くんのかよ。ここの社長ってどんなやつだった?」
「さあ? SD聖くん見て感激してたけど」
大きな誤解である。
「……変な奴」
「面白い人だったよ」
「社長の名前はなんて言うんだ?」
「あ」
シータの動きが止まった。
「……?」
「あたし、社長さんの名前聞いてくんの忘れちゃった」
まあ、世の中こういう事もある……(^^;)。
「善良なこの俺が……19号埋め立て地なんかに来る羽目になるとは。よくよくデンジャラスな仕事を引き受けたもんだ」
今日、アーマスはチャン・リン・シャンを尾行するために会社を早退している。
理由を考えつくのは結構大変だったが、とりあえず日本にアメリカから両親が訪ねてきているから、と苦し紛れの言葉で取り繕った。
案外すんなりと早退を認めてくれたのは、佐々木建設の社員は皆、家族を大切にしているせいなのか……それとも「使えねえ」新入りが一人早く帰ったところで、
「忙しいのは変わりゃしねえんだ。けえれけえれ」
ということなのか……。
できれば前者と思いたい。
19号埋め立て地、そしてその繁華街にあるBAR白薔薇。
どちらもカタギの出入りする場所ではなかった。だが、チャン・リン・シャンの足どりは、通い慣れていると言ってもいいものだった。
(社長の言っていた通り、ヤバそうな女だ)
ため息をついてチャン・リン・シャンの座ったボックスの隣に腰を下ろす。
チャンはソファに身を埋めるようにしてゆったりと座り、彼女の横には黒い背広の男が背筋を伸ばして座っていた。
「お嬢様……」
そう男が呼びかけるのが聞こえた。
店内は音楽がうるさい上に客の数も多く、隣のボックスといえども抑えた声量の言葉は聞き取る事ができない。
アーマスがポケットに忍ばせたマイクも、これではチャンの声を捕らえる事はできないだろう。
チャンの横にはBARのホステスが同席していた。
そのホステスの手を取って、なまめかしい愛撫を加えるのが、アーマスにも分かった。
思わず、赤面してしまう。
(こういう役は、やっぱり社長にやらせるべきだった)
結構純情な奴なのである。
そうしたアーマスの行動を、チャンは目の端で逐次追っていた。
彼の尾行には気づいていた。……いや、こうして尾行させるために、わざわざ真奈美を通じて情報をもらしたのである。
佐々木建設を配下に収めるこの作戦に、あたかも華僑の勢力が絡んでいるように見せかけること。「大人」という謎の人物をチラつかせる事で、神野によって勧められているブレーメ・シュトルム作戦、そしてそれに続くクリスタル・ナハト(水晶の夜)作戦から隠密たちの目を反らす事が目的だった。
彼らがいくら「大人」の事を探っても、答は出ない。
「大人」は架空の人物なのである。
そして「大人」の使者、として白薔薇に現れた黒い背広の男も、DGSのエージェントの一人に過ぎなかった。
「パーティでの、佐々木義一の反応が楽しみだわ」
そう呟くように言った声がアーマスの耳に飛び込んできた。
DGS主催のパーティの事は真奈美を通じてすでに情報が入ってきていた。DGSが日本での活動を本格的に開始するための……いわばお披露目パーティのようなものだ。政財界の大物が一挙に顔を揃える事になるだろう。
義一、浩二、西崎も……人工群島の大手企業である佐々木建設の代表として招待を受けていた。
(パーティで……何をする気なんだ)
アーマスは時折中国語らしい発音の混じる聞き取りにくい言葉に、必死に耳を傾けていた。
だが、聞き取る事のできたのは、当たり障りのない部分ばかりである。
「「大人」も本腰を入れて援護する事でありましょう」
とか、
「一門の尊厳にかけて……」
だとか言った黒服の方の相づちは比較的聞き取り易かったが、それだけでは何の事かさっぱり分からなかった。
二人の会話は、十五分ほどで終わった。
黒服の男が先に席を立ち、チャンは彼が店を出てもまだ腰を上げようとはしなかった。
ウィスキーのグラスを傾けて、ホステスの女に何かを囁いている。
その手の動きはさらに濃密なものになっていた。
店の中に、そのチャンを見つめている視線はアーマスのものだけではなかった。
いちばん奥の目立たないボックスから、チャンを伺っている一人の男……。
フリージャーナリストであり、DGSにアルバイトとして籍を置き、ブレーメ・シュトルム作戦で「広川書店」の社長とされた……雅一だった。
DGSにとって、雅の存在は獅子心中の虫であった。
その雅の目を社内の作戦から反らす事もまた、この白薔薇を訪れた理由のひとつだった。そしてチャンの企みは、見事に成功した。
「あの二人の背後を調べて頂戴」
ホステスにそう言って、チャンはその首筋に尖った爪をゆっくりと這わせた。
「ええ……すぐにでも」
滑るようななめらかな発音が、ホステスの唇から洩れた。
客の大半が集まったところですべての灯が消され、一階ホールの前庭にスポットが集中される。
前庭にもテーブルが置かれ、ガーデンパーティの用意がされていた。
すべての客の視線が集中する中、招待客の誰もが予想してなかった盛大なオープニングセレモニーが始まった。
大音響の行進曲が流れ、社旗を掲げたバイクを先導に一台のオープントップのメルセデスが駐車場から前庭に乗り付けたのだ。
閲兵式さながらに前庭に整列した社員たちに迎えられて、メルセデスから降り立った女こそ……DGS極東マネージャー、椎摩渚であった。
「極東マネージャーをつとめる椎摩渚がご挨拶を申し上げます」
前庭に作られた台の上に神野麗子が立ち、車から降り立った渚を誘導するように手をさしのべた。
「……まるで、ナチス気取りだな」
会場内にはそう毒づく声もあった。
だが、その「ナチス気取り」の固い印象の中で……アンバランスとも言える椎摩渚の豊満な肉体は男たちの欲望をかき立てるのに充分すぎるほどのものだった。
「お忙しい中、お運び下さいましてありがとうございます。DGS極東マネージャー、椎摩渚です」
渚はその男たちの視線を誇らしげに身に受けながら、だが少女の微笑を少しも崩さなかった。
簡潔な渚の挨拶が終わると、渚の立つ台の両わきに用意された巨大なシャンパンツリーに高級シャンパンが惜しげもなく注がれた。
「それでは……DGSと皆様の今後のさらなる発展を祝って……」
そう言って、渚はシャンパンを満たしたグラスを受け取り、乾杯の仕草を見せた。
パーティに集まった顔ぶれは、諏訪操の手回しによって予定以上のものだった。
政財界の大物が一同に介し、神野の企てを実行するのに最高の舞台が作り上げられていた。
そしてその中に、佐々木義一と佐々木浩二の姿もあった。
ふたりは離れた場所に立ち、目線を合わせる事もなかったが、DGSと椎摩渚に抱く嫌悪の念は同じようだった。
酒にも食事にも……ほとんど手をつけず、お義理で顔を出したのだという風情があらわだった。
「浩二さん……少しお時間を頂けるかしら?」
会場の隅の方で招待客の菱島駿河重工の会長の話に相づちを打っていた浩二に、神野麗子が声をかけた。
菱島駿河重工は宇宙開発の分野に一九〇〇年代から食い込んでいた大手企業である。バイオスフィア計画に名を連ねる企業のひとつでもある。その会長三橋剛蔵は、経済界の重鎮として知られる人物だった。
「神野さん……あなたとは関わりを持ちたくない。こうして今日伺ったのもその事をはっきりと伝えるためです」
三橋や周囲の者に聞かれないよう、浩二は声を潜めた。
「……義一さんのお嬢さん、六歳におなりだそうね。あなたも自分の娘のように可愛がってらっしゃるとか?」
「若菜をどうする積もりです」
「どうもしやしませんわ。私は噂を耳に挟んだだけですもの。あなたが姪のお嬢さんをとても可愛がってらっしゃるって」
その麗子の、試すような口ぶりに浩二は大人しく従うより他なかった。
麗子に案内され、会場の中心へと引き出される。
兄である義一の刺すような視線が、容赦なく麗子に浴びせられているのを、浩二は見逃さなかった。
絞首台に引き立てられる死刑囚の気分を浩二は味わっていた。
すでにパーティは佳境に差し掛かっていた。
オープニングセレモニーの時と同じように椎摩渚が壇上に立ったのはその時だった。
「皆様、ここでDGSの日本での活動を支えて頂くこととなる佐々木建設の新しい社長に就任される、佐々木浩二氏をご紹介します」
渚のその声と同時に、麗子に追い立てられるようにして浩二が渚と同じ壇上に昇った。
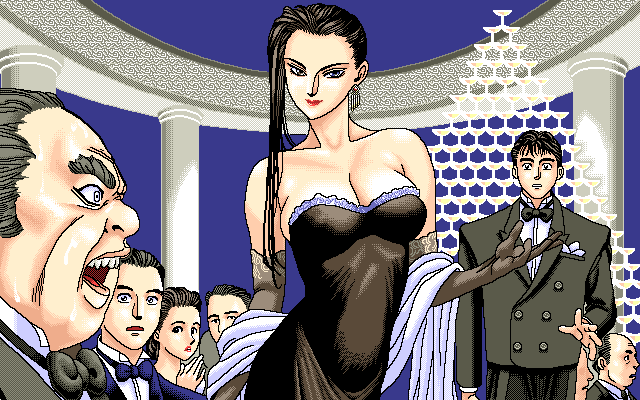
「不慮の事故に寄ってお亡くなりになられたお父上、辰樹氏のあとを継ぎ、浩二氏は佐々木建設をより大きな企業に育てたいと熱意をお持ちです。今後は宇宙開発の分野からは退き、環境問題に真正面から取り組む総合企業としての道を歩まれる確固たる信念をお持ちです」
渚の唇から流れる銀の鈴を震わせるような美しい声に、招待客は聞き入っていた。
自信に溢れる渚の微笑と……不安と怒りの綯い交ぜになった浩二の表情との対比は、見る者に様々な憶測を抱かせた。
「……あの女」
義一に同行した高槻が、思わず声を荒げて渚の立つ壇に歩み寄ろうとする。それを義一は鋭い声音で制止した。
「これ以上、恥の上塗りをするな」
そう言って、義一は壇上に立つ浩二を振り返った。
一瞬、二人の視線がぶつかりあった。
浩二がすがるような表情を見せたのが、義一には辛かった。これが浩二の策略でないことなど、良く分かっている。だが……そんな顔を見たくはなかった。
その弱さ故に、浩二はこうして利用され、追いつめられているのだから……。
「高槻、帰るぞ……」
そう言い放ってきびすを返す義一を諏訪操が見つめていた。
(神野さんの計画は……予想以上の成果を見せたようだわ)
そしてもう一人、渚の行動を見つめて険しい表情を晒している男がいた。
西崎昌明は、すでに度を越した酒量を口にして酩酊の状態にあった。その醜態にDGSの女たちが嫌悪の表情を露にしていることにさえ全く気づいていなかったのだ。
だが、壇上に立った浩二を見た瞬間に、酔いなどすべて吹き飛んでいた。
「何故……どうしてだ、渚」
突然、西崎はそう大声を発した。
その行動には、西崎を押さえる役を買ってでていたチャンも慌てずにはいられなかった。
「西崎様、少し召し上がり過ぎのご様子ですわね。こちらでお休みになっては? 今冷たいものでも……」
だが、そのチャンの手を振り払って西崎は壇上に立つ渚の方へと詰め寄ろうとしていた。
(もう少し……利口な男と思っていたが……)
壇の下に控えていた神野は、その西崎の姿を見て舌打ちした。
警備の者に合図を送り、西崎をパーティ会場から連れ出させる。
しかし招待客にとってそれは見応えのある余興だった。巨大な資本を持つ大企業を味方につけた妾の息子と、晴れやかなパーティを中座する、次期社長第一候補の長男と……そして策略に失敗したのだとありありとうかがえるもう一人の副社長。
この会場に集まったのは皆、利権という甘い汁を吸う蝿のような者たちばかりだった。 彼らにとって……他社の不幸こそ、決して冷めることのない贅沢なご馳走なのだ。
「渚め……何を考えている。私を出し抜いて、佐々木建設を潰す積もりなのか……」
そう呻く声をもらしたとき、扉が開いた。
「渚かっ?!」
西崎は怒声を上げて開かれた扉を振り返った。
だがそこに立っていたのは椎摩渚ではなく、屈強な警備部の男を背後に従えた神野麗子の姿だった。
「神野……貴様の差し金か! 私をこんなところに軟禁して、ただで済むと思ってはいるまいな? 渚を呼べ!」
「お静かに願いますわ、西崎さん」
いきり立つ西崎を冷笑するように、麗子の声は穏やかなものだった。
「あのお方から、伝言をお預かりしています」
「伝言だと? 渚はなぜここに来ない。貴様ごときに伝言をよこさせるとは、私も甘く見られたものだな」
「ご自分の立場を良く考えて、言葉をお選び下さいな。伝言は以下の通りです。西崎昌明名義の佐々木建設株をすべて椎摩渚名義に変更すること。これについては一週間の猶予を与えるという寛大なご処置がなされます。株はすべて、暴落前の値段で引き取る準備が整っています。……あなたにとっても決して損なお話ではないでしょう? 以上です。あのお方はもう二度とあなたに会う事はありません」
「株を……渚の名義にだと? 気でも狂ったか、そんなことをしなければならん道理がどこにある!」
激高して麗子につかみかかろうとする。
だがその足元は酒のせいでふらついていた。体勢を崩したところを警備員に二人がかりで押さえつけられる。
どう抵抗する事もできずに、ぎりぎりと床に顔を押しつけられて、西崎は上目遣いに麗子を睨んだ。
だが、麗子の冷酷な微笑がそれを悠然と見おろし、エナメルのハイヒールがその顔を乱暴にこづく。
「言葉を選べ、と私はそう言わなかったかしら? いつまでも大きな顔をしていられるとは思わないことだわ。あなたの身分は佐々木浩二が社長に就任次第、更迭されます。せいぜいそれまでに身辺を整理しておくことね」
「私が……易々とそれをさせると思うのか」
「あなたが手にかけた男と同じ目に遭いたいというのなら……それもいいでしょうね。……まさかそんな無様な真似をしようなんて考えないでしょうけれど、義一の側に寝返ろうなんて考えない事ね。佐々木建設の株暴落の裏であなたが何をしたのか……こちらにはあなたの両手を後ろに回すための証拠はいくらでもある事を忘れないで頂きたいものだわ」
「最初から、こうする事が目的だったのか! 渚を呼べっ! あの淫売をここに呼んでこいっ!」
そう叫んだ西崎の横面に、麗子のハイヒールが思いきり蹴りを入れた。
「この場で死にたくなければ、不用意な発言は控えることね、西崎」
西崎の鼻や唇が切れて血が流れ出し、敷き詰められた高価な絹織りの絨毯を汚した。
「言ったはずだ。あのお方は、もう二度とおまえに会う事はない。今後すべての処理はこの神野麗子が担当する。それを……よく覚えて置くことだ」
「この……小娘が」
ぎりっと西崎は唇を噛んだ。
せせら笑うよう神野麗子の悪意に満ちた表情がその視界に灼きつき、そしてつぎの瞬間、再び蹴り下ろされた衝撃で気を失った。
「副社長! 西崎副社長っ!」
ロイヤルスィートを出たところに、西崎の秘書である牧田晴彦が立っていた。
殴られたらしいあとが、牧田の顔にも無惨に残っていた。
「ああ、大丈夫だ。渚がどこにいるか分かるか」
「最上階のロイヤルスィートです。しかし……建設省の事務次官が来ているようで、とても近寄る事はできません」
「くそっ、あの女狐め、どこまで私をコケにするつもりだ」
「副社長、血が……」
そう言って、牧田はハンカチを差し出す。
だがその手を西崎は苛立たしげに振り払った。
行きどころのない怒りが、西崎の身体の中にたぎっていた。この屈辱をはらさずにおめおめと尻尾をまいて逃げる事などできるわけがない。
「無茶な事はおやめ下さい。ここにいるDGSの警備員は皆、銃を携帯しています。副社長おひとりでやり合う事などできません」
牧田の必死の形相が、ともすれば暴走しようとする西崎をなんとか押し止めた。
「このまま……このまま終わらせはせん。例え義一と組んででも、必ずDGSの鼻を明かせてやる」
「義一副社長と……? しかし……」
牧田は渋い表情になった。
神野麗子の脅迫めいた言葉があろうとなかろうと、そんな事は不可能だった。義一がDGSと西崎の接触に気づかずにいるはずはない。
広川書店による株の買い占めとその後の株暴落の裏に、西崎の姿がある事などとうの昔に掴んでいるはずだった。
DGSの庇護を失った今、西崎がどういきり立とうと、義一はかなう相手ではないのだ。
辰樹が二十代前半にして父から社を受け継ぎ、業界トップの地位にまでのし上がっていく過程をずっと見つめてきた西崎になら、それは理解できていて当然の事だった。
隠密と称して社員の中に腹心の部下を潜ませてきた辰樹のやり口を、義一はそのまま受け継いでいるのだ。
だが、それをすべて分かった上で……西崎はそれでもここで膝を折って敗者として葬られる道を選ぶことはできなかった。
副社長という肩書きでありながら、その実佐々木建設という大企業を支え、育て上げてきた。そして辰樹の死によって、今度こそ社を意のままに操る事ができる……その野心が、そのうすっぺらなプライドが、西崎にとって生涯をかけて獲得し得たたったひとつのものなのだ。
それを失う事は西崎にとって……辰樹の野心の犠牲となり、常に泥をかぶり、辛苦を嘗めて生きてきたこれまでの人生のすべてを失う事だった。
失う事はできない。
これまでの苦労を……。
辰樹の野心に寄生して得たこの地位を……捨てる事などできはしない……!
「洋二を呼べ。どんな手を使っても、義一に私の地位を守らせるんだ」
「……洋二を……使うんですか」
「そうだ。つべこべ言うな。もともと洋二はこの時のための駒だ。DGSが私の株を奪い、私の隠し口座の金を操作するまでに……何としても義一を懐に引き込むんだ」
張り飛ばしそうな勢いで西崎は牧田に命じた。
「――あの、辰樹の娘を使って……!」